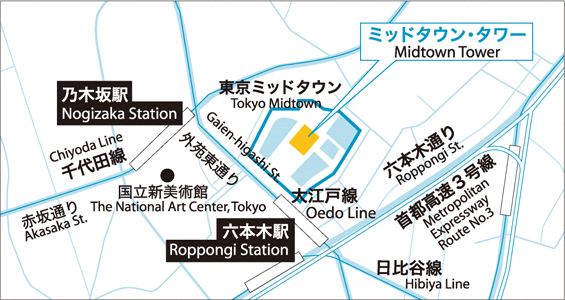昨今、円安・米ドル高が取り沙汰される機会が増えていますが、円は、ニュージーランド・ドルや豪ドル、ユーロ、スイス・フラン、英ポンド、人民元などに対しても軟調です。そこで、円について、通貨の総合的な価値を示す実質実効為替レート(左下グラフ参照)を見ると、2023年8月に1970年8月以来53年ぶりとなる安値をつけた後も概ね下落傾向にあり、最安値を更新中です。つまり、米ドルにとどまらず、幅広い通貨に対して円安基調となっています。ちなみに、1970年と言えば、ニクソン・ショック(ドル・ショック)の前年であり、1米ドル=360円の固定相場制の時代です。
通貨の実力を表す、実質実効為替レート
実質実効為替レートは、特定の2通貨間の為替レートだけでは捉えられない、通貨の総合的な実力やその変動を見るための指標です。国際決済銀行(BIS)の実質実効為替レート(Broadベース)の場合、約65の国・地域の通貨を対象として、貿易額や物価水準などを基に算出されています。その特徴の1つとして、他の国より物価上昇率が高ければ上がり、低ければ下がる傾向があります。
円の実質実効為替レートは、1995年4月に最高値をつけて以降、振れを伴ないながらも、水準を切り下げています。その主な背景は、「失われた30年」とも呼ばれる、バブル崩壊後に続いた低成長やデフレです。また、日銀が2013年に異次元緩和を開始し、2016年にはマイナス金利政策や長短金利操作を導入するなど、デフレ脱却に向けて長期金利を抑え込む政策を採り、内外金利差が開いたこと、さらには、低金利の円で資金を借り、高金利通貨で運用する、「キャリー取引」が活発となったことなども、円安要因となりました。
立場によって異なる、円安の功罪
円安は、訪日客による消費の拡大につながるほか、輸出産業にとっては、価格競争力や収益の改善に寄与するなどとして、プラスとされています。ただし、輸出から海外現地生産への移行が進んだことに伴ない、円安による輸出数量の押し上げ効果は低下しています。また、家計や、輸入品に依存する産業にとっては、円安は負担増となるため、生活や事業にとってマイナスと考えられます。
当面の経済・物価見通しなどに基づくと、今後、欧米などでは利下げが、日本では利上げが予想されており、内外金利差の面からは、円に押し上げ圧力がかかるとみられています。ただし、日本は世界的にみても急速な少子高齢化や、低い労働生産性などの構造問題を抱えており、これらに対して有効な対応がとられなければ、中長期的には円安が続く可能性も考えられます。
分散投資という対応
為替レートは、様々な要因で時々刻々と変動することから、予想は容易でありません。ただし、資産運用においては、投資対象を円資産に限定せず、相対的に高い成長が見込まれる複数の国・地域の資産(通貨)に分散することで、リスクを抑えながら、当該国・地域の成長の恩恵に浴することが可能になると考えられます。
![【図表】[左図]円の実質実効為替レートの推移、[右図]主要通貨の実質実効為替レートでの騰落率](/files/market/rakuyomi/images/rakuyomi_vol-1997.jpg)
- BISや日銀などの信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成
- 上記は過去のものであり、将来を約束するものではありません。