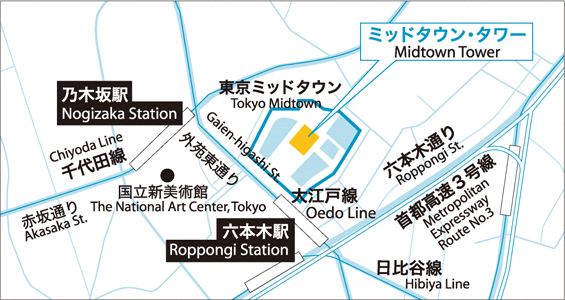長期的に良好なパフォーマンス実績を根拠に、株式投資は米国株式だけで十分との見方が散見されます。そこで本稿では、日米株式の局面別のパフォーマンスや、リターンの差の要因を分析し、米国株式だけでなく日本株式にも目を向ける必要性について考えます。
過去の米国離れ局面では日本株式が優位
2006年1月~2025年5月の期間(以下、全期間)で、日米株式のパフォーマンス(円換算ベースの年率換算値)を比較すると(左下図【A】)、米国株式の平均リターン(算術平均)は12.8%と、日本株式の6.2%を大きく上回りました。また、リスク(リターンのばらつき)に対し、どれだけリターンが得られたかを示す運用効率は、日米株式を組み合わせたどのパターンよりも、米国株式単独の場合が良好でした。そのため、米国株式だけで十分との見方には一定の根拠があるといえそうです。
もっとも、米国株式のリターンが世界株式(除く米国)対比で劣後し、米ドル安が進んだ、米国離れ局面(全期間の約3割で発生)では、日本株式がリターン、運用効率とも米国株式を大きく上回りました(左下図【B】)。今年に入り、米トランプ政権の政策への懸念から、経済・金融面で米国一強が続く「米国例外主義」の後退が指摘されています。そうした局面の期間が長引いたり、頻度が高まれば、日本株式の組み入れが有効になるとみられます。
企業活動の本質部分のリターン寄与は大差ない
全期間中のリターン(データの都合上、幾何平均)の寄与分解に視点を移すと(右下図)、日米株式のリターンの差は、為替(円安・米ドル高)による米国株式の円換算後リターンの押し上げと、バリュエーション格差の拡大――即ち、米国株式への評価が日本株式と比べて高くなった――が主因だったとわかります。他方で、企業業績見通しや配当など、企業活動の本質部分の寄与では大きな差はなく、期間によっては、日本株式が米国株式を上回る局面も観察されました(右下図【参考】)。
米国離れ局面が続けば、バリュエーションや為替が米国株式のリターンに従来ほど寄与しない可能性が考えられます。もちろん、日本株式についても円高・米ドル安による企業業績見通しの悪化リスクがありますが、日本企業はこれまで海外進出などを通じて為替変動への耐性を強めるとともに、稼ぐ力や株主還元を強化してきました。そのため、企業活動の本質部分の寄与を反映し、日米株式のリターン差が縮小する余地もあるとみられます。
米国株式のパフォーマンスは長期的に優れており、引き続き株式投資の中心的位置を占めるとみられます。しかし上述のように、米国離れ局面での過去のパフォーマンスや、企業活動の本質部分のリターン寄与などを考慮すると、日本株式にも目を向ける必要性が高まっていると思われます。
![【図表】[左図]日米株式のパフォーマンス特性、[右図]日米株式のリターン寄与分解](/files/market/rakuyomi/images/rakuyomi_vol-2108.jpg)
- 指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当該指数の算出元または公表元に帰属します。
- 上記は過去のものおよび予想であり、将来を約束するものではありません。