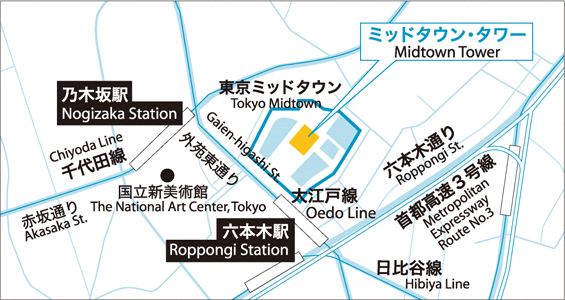規模別指数からみる日本経済の姿
1999年末以降の株価推移(下の折れ線グラフ)をTOPIX(東証株価指数)とその規模別指数で見た場合、値動きに違いがあることがわかります。
TOPIX採用銘柄の時価総額上位30銘柄で構成された指数であるTOPIXコア30指数(以下、コア30)の値動きは、2012年頃には▲70%(1999年末比)を超えて低迷し、足元でTOPIXがプラス(同)となる中でもマイナス圏を脱せずにいます。
一方、TOPIX採用銘柄の時価総額順位501位以下の銘柄で構成された指数であるTOPIXスモール指数(以下、スモール)は、値動きの振れ幅は大きいものの、足元ではTOPIXの2倍以上の水準にあります。つまり、2000年以降、日本株式が長く伸び悩んだ背景には、TOPIXの時価総額の40%強を占めるコア30(下の円グラフ)の低迷が大きく影響したと考えられます。
コア30の構成銘柄である大企業は、2008年のリーマン・ショックやその後の急激な円高の影響などを強く受け、業績が振るわない期間が続きました。
一方、スモールには、ニッチ市場ながらも国内外を問わず高い競争力を武器に業績を伸ばした企業や、新しい市場を開拓した新興企業などが含まれており、そうした企業の成長力が、高いパフォーマンスにつながったと考えられます。
東証の市場改革が今後もたらす影響
2022年に市場区分の見直しが行なわれて以来、東京証券取引所(東証)は、資本コストや株価を意識した経営、グロース市場の機能発揮など、企業経営のあり方に関する提言を公表しています。こうした提言には、経営のあり方を見直すことが企業の競争力や収益力を強化し、株価上昇につながるという期待が背景にあります。
コア30の構成銘柄では東証の提言への対応を終えている企業が多い一方、スモールではいまだ対応中という企業が相対的に多いと考えられ、この先、提言内容がスモールにも広く浸透することが見込まれます。
そういった意味でも、スモールには伸びしろのある銘柄が多数あると言えます。ただし、スモールの銘柄の中には、企業規模の小ささから経営が安定しない企業や、法制面の変更などで事業が立ち行かなくなる企業などもあり、大型株に比べて銘柄選択の難易度は高まります。さらに、投資家の資金面での制約なども考慮すると、個人で投資するにあたっては、投資信託など専門家の力を利用することが有効と考えられます。
![【図表】[左図(円グラフ)]TOPIXの規模別時価総額比率(2025年5月末時点、浮動株ベース)、[右図(折れ線グラフ)]TOPIXと同規模別指数の推移(1999年12月~2025年6月、月末値)](/files/market/rakuyomi/images/rakuyomi_vol-2112.jpg)
- 信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成
- 上記は過去のものおよび予想値であり、将来を約束するものではありません。
- 指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当該指数の算出元または公表元に帰属します。