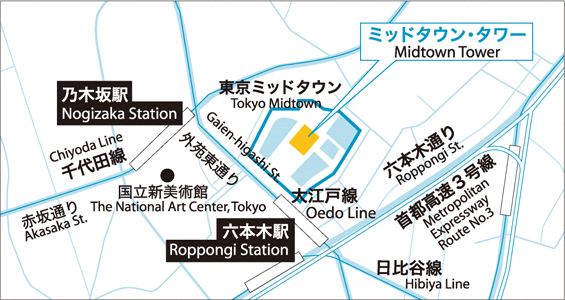昨年、東証(東京証券取引所)の上場企業数が2013年の大阪証券取引所との統合以来、初めて減少に転じました。今年に入ってからも、上期(1-6月)の上場廃止件数が58件と前年同期の51件を上回るなど、上場企業数が減少傾向となりつつあります(左下グラフ)。
こうした中、本稿では、日本で上場企業数が減少している背景や、過去の米国との類似点などに触れつつ、それが株式市場にとってどのような意味を持つのか、考えてみます。
上場維持のハードル上昇などが上場廃止を促進
足元で日本の上場企業数が減少している背景には、主に2つの要因があるとみられます。
1つ目は、上場維持のハードルの上昇です。2015年のコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)導入以降、上場企業には経営の透明性確保や企業価値向上などに向けた対応が強く要求されるようになり、さらに2022年には、東証の市場再編に伴ない、上場維持基準が新規上場基準と同程度に厳格化されました。また、今年4月からはプライム市場上場企業を対象に重要情報の英文開示が義務化されるなど、情報開示コストも増加しています。これらを受けて、企業は、資金調達の容易性や知名度の獲得などの上場のメリットと、各種基準の達成や情報開示にかかる負担といったデメリットを、より慎重に比較するようになっています。
2つ目は、「物言う株主」と呼ばれるアクティビストの活動の活発化です。アクティビストが業績向上や資本政策について厳しい株主提案を行なう事例が日本でも増える中、上場企業が経営の自由度を確保するために、株式の非公開化を選択する例もみられるようになっています。
過去四半世紀弱で米国の上場企業数は大幅減
ここで米国に目を転じると、1990年代後半以降、上場企業数が長期にわたって減少傾向を辿ったことがわかります(右下グラフ)。
その背景には、①2002年のSOX(サーベンス・オクスリー)法制定をきっかけに、上場企業の情報開示や投資家保護に向けた規制が強化されたこと、②1990年代後半以降、アクティビストが運用する投資ファンドの認知度向上に伴ない、その活動が活発化したこと、などがあったと指摘されており、足元の日本との類似点が見いだせます。
また、米国では、プライベートエクイティ(未公開株式)ファンドが、上場を選択しない企業への資金の出し手になりましたが、日本でも近年、海外の大手プライベートエクイティファンドの参入などによる資金調達手段の多様化が期待されています。
日本でも上場の質がより重視される時代が到来
上記のような過去の米国との類似点を踏まえると、日本の上場企業数の減少は一時的なものではなく、今後も継続すると考えられます。このことは、上場企業の質がより重視される時代が日本でも到来し、より選別された優良企業群に投資できる環境へ変化しつつあることを示していると思われます。
![【図表】[左図]日本(東証)の上場企業数と上場廃止件数の推移、[右図]米国の上場企業数の推移](/files/market/rakuyomi/images/rakuyomi_vol-2119.jpg)
- 東証や世界銀行などの信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成
- 上記は過去のものであり、将来を約束するものではありません。