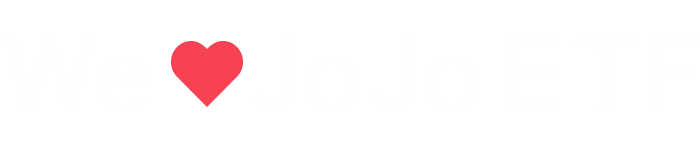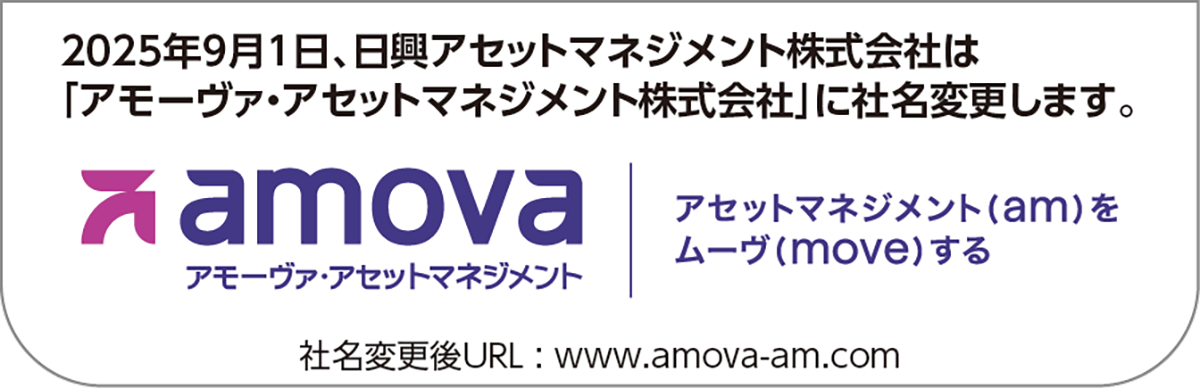- 2023年6月23日
vol.41 どうして株式に投資した方がいいの?
投資を避ける日本人
日本人の株式投資への恐怖心の理由はいろいろあると思う中で、私が気になるものを2つ挙げます。
1つめは、昭和の映画や小説の影響を受け、そのイメージに引きずられているケースです。たとえば「株式投資はバクチである」「ずるずる引き込まれて夜逃げの恐れがある」「悪い人や政治屋がずるく立ち回って裏金を作るために使う悪事」といったイメージです。
2つめは、株式投資はとても詳しい人がやるべきことで、素人はやけどする、横にだれかついていてくれないとできない、いつも市場を注視して動きに詳しくならないとできない、というような理由です。
確かに、2000年7月に日本に金融庁ができ、株式市場のスキャンダルや詐欺への監督が厳しくなることで「事件」として次々と報じられるようになり、すっかり株式投資の印象が悪くなっている人もいると思います。
また、株式投資というと、銘柄選択と頻繁な売買をする人がもともと多く、さらにインターネットの普及や取引手数料の自由化で元金融マンを含めデイ・トレーダー*1が増えてきました。雑誌などの話題の中心が、億り人*2、テンバガー*3、カリスマ投資家などになってしまったのは、投資が遠い世界の話に感じられるかもしれません。
*1 一日で収益を上げるような短期取引を行う投資家
*2 株式投資や暗号資産取引(仮想通貨取引)などで億単位の資産を築いた投資家
*3 株価が10倍以上に成長する銘柄
次節で述べるように、日本人はもっと株式に投資してみてもいいと思うのですが、いまのところ、「Invest in Kishida」の名言を述べ、所得倍増プラン元年(貯蓄から投資へ)を導く岸田内閣の資産公開によれば、首相は株式もファンド(投資信託やETF)も保有していないようです。政治家は、昭和のころに公共投資を握る一方で建設銘柄に投資するなどと思われてきた名残で、いまも純粋に株式投資をすることは少ないようです。
私としては、個別銘柄を自ら選んで投資することは難易度が高いため、今以上に多くの個人投資家が取り組まなくてもいいのではと考えます。投資のスリルを楽しんだり、資金をかなりすり減らすリスクを取りながらも株価が10倍になることを目指すのは株式市場の活性化に資するので歓迎しますが、金融の仕事の経験もなく、まったく違うことを毎日気にして仕事や生活をする人たちが「横にだれかついてくれないと投資なんて無理!」などと思うのは当然だからです。

はじめは債券よりも株式で
株式にだけ、会社が(誰か他人が)一生懸命働いた成果の分配に参加できる権利が存在しています。株式は、債券のように決められた償還金も利息の支払いの約束もありません。儲けたら配当をもらえる期待があるだけです。ただし、株主は経営者を選ぶ投票権と利益を配当にまわすことを決める権利を持っています。この絶妙なバランスが、債券、預金との違いを作り出します。
債券や預金では、企業やひいては経済の成長に参加できません 。株式投資家は、会社への参加を通じて、会社に関わる人々(経営者や従業員、ある意味では顧客や取引先も)の努力と工夫の成果を、増える分には制約なく受け取る可能性があるのです。こんな金融商品が昔に発明されたのはなんともすごいことだと思います。
しかも株式投資家は、特定の会社に集中しなくてよいという特典があります。ある会社で働く経営者・従業員は実はその会社の盛衰に生活上大きな影響を受けます。しかし、株式投資家は、投資した金額以上を失わないというだけではなく、たくさんの良さそうな会社に幅広く投資するチャンスがあるのです。小口に分かれていることは株式のとても大事な性質です。債券や金も投資とは呼ばれますが、どれも人間の努力と工夫を上限なく分配されるものではありません。気軽に株式に投資できる環境が整った戦後の資本の民主化などに感謝して、人間の努力と工夫の果実を受け取ることができる株式投資に参加したいものです。
フランスの経済学者トマ・ピケティが述べたように、長い世界の歴史を調べると、投資家(貴族の農園経営などまで含んでいる壮大な研究ですが)は、株式投資ではインフレを除いておよそ3パーセントのリターンを平均的に獲得できると言っています。何もしなければゼロです。ちょっと大げさに言えば、株式投資家になることは資本家になることであり、人間の努力と工夫の成果を、その事業のリスクを取ることによって参加することなのです。
事業のリスクはいろいろあります。例えば、どんなに良い経営者と従業員のいる日本の輸出企業でも、円高になると帳簿上は利益が減ります。努力や工夫と関係ない変動が起こるので、長期的なリスクを取る資金が株主として必要になるのです。もちろん経営者が経営判断を間違うリスクなどもあります。株式投資家は世界中のたくさんの銘柄を持つことで、このような個別の事業のリスクなどを小さくすることができます。

株式投資はファンドでと考える理由 ~神山解説
しかし、ここまで読んできた投資未経験者であれば、株式投資は全然簡単じゃないとお気づきだと思います。世界中にあるたくさんの株式に少しずつおカネを投資するなど面倒だし、小口とは言え1銘柄10円から投資できるわけでもないのだから、最終的にたくさんの銘柄に分けて投資をするには大金が必要となってしまう、とお気づきでしょう。
だからこそ、株式の次の発明といえるファンド(投資信託やETF)が役に立ちます。これは、個人のおカネをたくさん集めてたくさんの株式に投資する仕組みです。つまり、世界中の幅広い銘柄をプロの運用者であるファンドマネージャーが買い集めてくれて、必要な調整をしながら管理運営してくれるのです。銘柄を細かく調べたり選んだりする必要はありません。その投資のプロセスがよさそうかだけ考えておけばよいのです。
そもそも、ファンドは、素人のために「うまいこと儲けてくれる」仕組みではありません。それぞれ決められたプロセスで運営されます。ですから投資をよく知らない人が銘柄を細かく調べたり選んだりする必要はありません。その投資のプロセスがよさそうかだけ考えておけばよいのです。
ここで知っておいてほしいことは「分散とバランス」です。できるだけ特定の国だけの株式投資にしないこと、元本保全のための預貯金、もしもの時のための保険などとバランスを取ること、これらは特に経験が少ない人に向いていると考えます。分かりやすいから、為替変動リスクが嫌だから、と狭い範囲に投資をするほど、リスクも偏りますので注意してください。元本保全的だけど少しはリターンが欲しいなどの理由があれば債券投資もいいと思います。
とりあえず最初の投資では、10年以上の期間でインフレプラス3パーセントのリターンという目標を置いてみましょう。そうすると株式を個別にたくさん持つ必要がないことに気づきます。
最初に肝心なのはどの銘柄か、どのファンドかよりも、いつごろどのくらいにしておきたいか、という目的・目標です。1年で株価2割上昇などという短期勝負は避け、たとえば20年たったら孫にお年玉を多くあげたい、海外旅行に行きたいといった長期の使い道の想定をしてみてください。学費など必要な資金は元本保全型で、楽しい(老後などの)消費を投資の目的にすると、価格が上下するリスクにも耐えやすくなります。
この記事に関連する日興アセットのETF
世界の株式に分散投資ができるETF
1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (愛称:上場MSCI世界株)
<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。