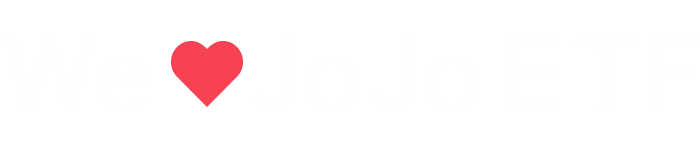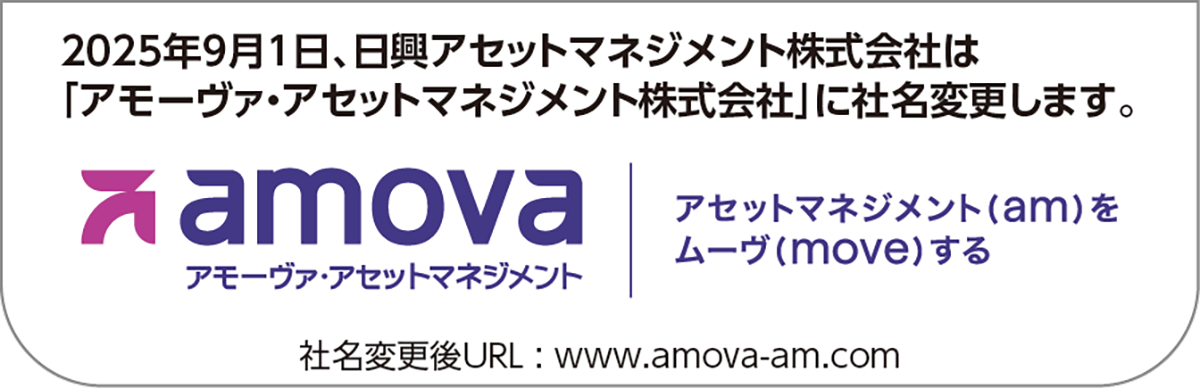- 2023年8月2日
vol.42 海外投資家からの日本株への質問
円安で日本株が上がり、円安終われば下落?
日経平均が3万円を超えたところから、外国人の日本株買いが強まっています。現在の日本株の上昇は、まず今年のコロナ禍からの正常化で、旅行やビジネスが元に戻ることへの期待によります。そしてさらに、人手不足をきっかけに賃金が上昇し、インフレ基調になることで、企業の活動が積極化し長らくの低迷から脱却する可能性にも期待が寄せられます。
しかし、最近受けた海外投資家の質問のひとつは、株高と円安の関係でした。円安で株高になるのが日本市場の特徴ですが、日米の金利差拡大が7月27日のFRBの政策金利引き上げで継続しており、これからも米国の金利高と日本の金融緩和継続が日本株の上昇に必要か、という趣旨です。私の答えは、「そうではない」です。
過去の為替と日本株との相関を見ると、アベノミクスの時にドル高円安と日経平均の上昇との関係が強いので、そのように思われます。確かに、この時は、円安が進んで輸出企業の帳簿上の売上が上がったので、見栄えのいい決算が増えて、日本株の株高が正当化されました。しかし、長期的にみると、為替水準と株価に本質的な関係はないと考えます。
短期的には、「帳簿上の」とわざわざ書いたように、円安は輸出企業の売上の円換算額を増やしますが、実は、ドル建ての輸出品の価格は同じ、しかも売れる数量が同じであることが多く、企業は張り切って生産や在庫を増やす必要がありません。その年のボーナスを増やすことはできても、将来の売上の伸びを期待できず、設備投資を増やしたり人員を増強したりする必要もないのです。長期的には、輸出企業は為替よりも売上数量、簡単に言えば輸出する箱の数が増えることで成長します。数量で売れ行きが良いということは、在庫も減るので生産を増やしたくなります。人手を集め、足りなければロボットを採用するなど設備投資にも熱心になるでしょう。為替と数量では輸出企業の活動がまったく変わるのです。

これに加えて、コロナ禍からの回復は、内需を含めた日本全体の人手不足を呼び起こしました。つまり、外需だけではなく内需もヒト、モノ、カネが不足する状態になっています。内需の回復は為替とは関係が薄いです。
こう考えると、円高でも日本経済が大きく成長する局面にあることがわかります。米国などの成長率が低くなっても(景気減速)大幅な後退(マイナス成長)に見舞われなければ、日本の輸出業の数量が(成長率は低くとも)高い水準を維持し、コロナ禍から回復する経済と相まって人手不足と賃上げ、設備投資積極化、資金需要の回復、そして企業活動の活発化で良いインフレ状態への移行の可能性が高くなります。
インバウンドの増加など円安であるほど伸びる業種もありますが、ドル円が110円程度でも十分安いとされた日本の物価なので、140円から150円へとドル高が進展する必要はないでしょう。今後、米国のインフレが鎮静化し、金利上昇が止まり、ゆくゆくは金利が低下してドル高が修正されるとしても、日本のヒト、モノ、カネの不足状態は続くとみており、為替と株の相関は低下するとみています。
世界のインフレの影響で、日本は長年のデフレ下から脱却できる?
こちらも海外投資家からよく聞かれる質問です。世界的なコロナ禍と行動制限による供給不足、政府の補助金や一時金の支出による超過需要に始まった世界的なインフレは、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格上昇にも煽られてしばらく強い動きとなりましたが、日本が世界に引きずられてインフレになるわけではないと考えています。
インフレは各国経済の事情により起こる国内問題とみてよい、と思います。例えば、世界的なエネルギー価格の上昇で光熱費が上がっても、国内の貯蓄が尽きればインフレは終わり、単に不景気が残るのです。
しかし、上で述べた理由から日本がデフレ環境からインフレ的な状態になる可能性は高まっています。まず、人手不足が賃金の上昇につながります。輸出関連も国内企業も同時に幅広く人手不足に陥ったのは、リーマン・ショック後初めてと言えるでしょう。賃金を上昇させても売り上げが上がるのですから利益率の低下の恐れは小さいです。次のステップとして、人手不足は設備投資を呼び起こします。これまでは古い機械のメンテナンスだけにおカネを使い、利益温存に努めましたが、もっと性能がいい機械を入れたり、ロボットで人手不足を補ったりするようになるでしょう。円安で帳簿上の利益だけが出るだけの時とは違い、経済活動は活発になります。
そのため、これまで景気サイクルで上下動するが成長軌道に乗っていないとみなされていた日本株を、海外投資家がさらに買い増していくはずです。アロケーションをアンダーウエートからニュートラルに引き上げる動きはまだ始まったばかりです。デフレ環境からインフレ環境に構造変化を起こす日本への興味は高まるでしょう。

個人投資家は、淡々と資産形成を ~神山解説
これまで述べてきたような背景から、もし日本株を完全に持たないようにしていた国内の投資家がいるとすれば、日本を買うチャンスでしょう。
投資の経験が長い人で日本株を持っていない人は少ないので、これまで通りで良い人も多いかもしれないです。あれこれ目先の変化に乗り換えせざるを得なかった日本株運用は、どっしり構えても大丈夫となる可能性があります。
日本株のリスクは、このような千載一遇のチャンスでも日本の経営者自身が半信半疑となり、なかなか設備投資や賃金引上げに進まないことです。2023年については、インフレを越えない程度の賃金上昇しか実現していません。また、機械設備への投資は増えていますが、まだ大手企業に留まっているようです。24年も賃金上昇と設備投資が継続的に拡大する兆しを待つ状態です。これまであまり積極的に打って出ないほうがうまくいっていた日本の経営が、この機会に変化すれば、その成果を勝ち得ることができそうです。
海外投資家の質問には、上場企業がPBR(株価純資産倍率)1倍以上にするように東証がモニターすることや、バフェット氏の日本の商社株の買い付けへの興味が含まれることもありますが、長期的にはそれほど重要ではないと思います。上場企業のPBR1倍は、外国人が株式をたくさん買うだけでもある程度実現してしまうので、企業がROE(自己資本利益率)を高めていこうとするかわからないです。さらに、PBR1倍になればモニターが終わりと考えると、ある程度以上に日本株の指数は上がらないことになります。また、バフェット氏が日本の商社だけを買っても日本株の指数全体が上がるとは言えません。
私たち国内投資家は、淡々と世界の株式に投資して、人間の努力と工夫の成果に参画することが求められます。日本がいいから悪いからとドタバタせず、淡々と日本を含む世界に投資しておくことで十分です。それをベースに、興味のある成長機会(ロボット、フィンテック、人工知能など)への投資を少し上積みすると良いポートフォリオになる人が多いと考えます。
この記事に関連する日興アセットのETF
日本株に投資ができるETF
1308 - 上場インデックスファンドTOPIX (愛称:上場TOPIX)1330 - 上場インデックスファンド225 (愛称:上場225)
1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ) (愛称:上場日経225(ミニ))
世界株に投資ができるETF
1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (愛称:上場MSCI世界株)
<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。