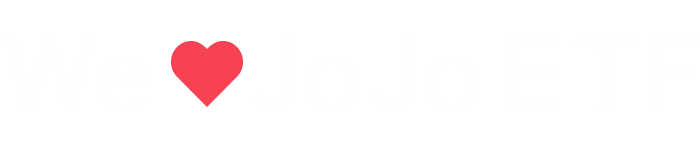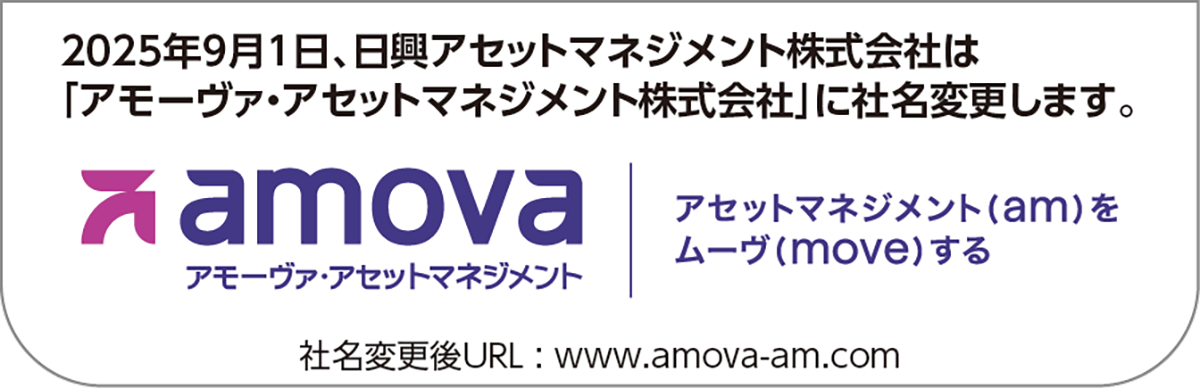- 2023年8月30日
vol.43 アメリカの国債格下げはこれから市場にどう影響する?
フィッチの米国債格下げの影響は軽微とみていい理由
2023年8月、大手格付会社のフィッチ・レーティングス(以下、フィッチ)は米国債の格付けを最上位の「AAA」から「AA+」に引き下げました。米国国債をAAAだから投資する、AA+だから投資対象ではないという区別をする投資家はめったにいないでしょうから、今回の格下げが市場に悪影響を与える可能性は今後低いとみています。
そもそも米国債の返済能力を格付けの上下動で表現する必要がないのでは、と考えています。新興国の国債であれば、政治が極端に動きがちで、格付けに注目すべきでしょう。ギリシャ危機など欧州の先進国に例外があるとしても、そもそも国の借金の返済能力は、税金を集める権力と能力に依存しているのです。そのため、先進国の国債の返済能力を現状のような格付けで考える必要があるのかすら分かりません。
社債であれば格付け会社の存在は重要です。そして、社債は税金をかけて返済することはできませんが、国債は基本的にできるはずです。だから「ソブリン*」と呼ばれるのです。一部の国では、税金を集めるべき相手を捕捉していない、あるいは私兵がいて税金を集められないなどの状態にあるのですが、米国など主要国については、あまり返済リスクの変化を細かく見るほどではないと思います。
*ソブリン(Sovereign) :「国王」「最高の」などを意味し、国債や政府機関債など、各国政府や政府機関が発行する債券の総称。
今回の2023年8月のフィッチによる最上位「AAA」から「AA+」という1ランク引き下げは、2011年8月にS&Pグローバル・レーティング(以下、S&P)が実施して以来12年ぶりとのことです。米国債格下げの理由が「財政、債務問題を含め、過去20年間にわたりガバナンスが悪化している」とのことなので、20年がかりの話を持ち出して、10年前の他社にいまさらながら追随したと言えなくもありません。この点も今回の格下げの重要性があまりないとみる理由です。

米地銀の格下げの影響は少し気を付けたほうがいい
フィッチという格付会社は、今回いくつかの米地銀の格付けをまとめて引き下げました。その後S&Pも地銀5行の格付けを引き下げました。こちらは少し気にしています。
アメリカには、いろいろな特徴のある地銀がたくさんあります。2023年3月のシリコンバレーバンクの破綻が問題になったことは記憶に新しいですが、預金者が少数であるという特徴がありました。同じような地銀にはFRB(米国連邦準備理事会)の監視も強まる一方、大手と合併する例も出ました。
格付け引き下げのリスクは、その銀行が市中で借りているおカネの借り換えが難しくなることです。調達金利が上がったり、調達額を減らすことになったりすると、銀行自身が融資先について額を減らしたり金利を引き上げることになり、その影響が地域に広がってしまうのです。
特に、いま注目されているのが、アメリカの商業用不動産の不調です。コロナ禍後にオフィスに人が戻らない傾向にある地域では、不動産の家賃収入が減ったままとなり、価格下落にもつながっています。地方のオフィスビルは小規模の不動産業者が保有していることが多く、地銀の融資態度が悪化するとデフォルトリスクが高まります。そうなると結局地銀経営に悪影響が跳ね返ってきてしまいます。このように、地銀の格下げは、地銀の借り換えリスクを通じて地域経済の悪化につながる恐れがあります。
米経済の裏には、FRBがいつまで高金利を続けるかというリスクが横たわっています。FRBは景気が悪くなるとしてもインフレを止めることを優先することを昨年から言ってきましたから、インフレ次第で金利が高止まる可能性があります。金利水準が高いままだと、借金が多くてもなんとか頑張って借り換えを乗り越えてきた不動産業者も「音を上げる」恐れが出てきます。当社は、FRBは来年早々にも利下げを始めるとみていますが、家賃収入低下に悩む不動産業については、インフレによる金利高でリスクが高まってしまう点を考えに入れる必要があります。
一方で、イエレン氏が財務長官であることは米国金融機関にとってはラッキーだったと思います。前職はFRBの総裁でFRBとの関係は当然強く、しかも銀行監督の経験が長いので勘所を知っていると思います。シリコンバレーバンクの件では素早くFRBと共同で預金保護を発表しました。銀行経営が不安定になるときのやり方をすでに作っているという安心感はあります。また、銀行システムが悪化するとそれ自体が経済に悪影響を与えることもよく知っています。この点では、地銀のショックは個別には起こっても、全体を揺るがすことにならないと想定してよいでしょう。

日本人投資家と米国債 ~神山解説
米国債投資に話を戻しましょう。格付けの引き下げで、現実に返済能力が低下しているようにも見えませんし、長期的には債券価格に影響を与えないとみています。米政府が適切に行動しているように見えます。
米国では、議会多数派が共和党で、大統領が民主党とねじれているので債務上限引き上げ問題という米国独特の「政治ショー」がしばしば繰り広げられます。これは、国債発行額が実態ではそもそも多いのに、毎年枠を引き上げて現実に合わせる必要があるように決めてあることが原因です。それ自体が政治ショーのための無責任な(投資家側としては)制度にみえますが、だいたい他の政策との取引の条件にされるのであって、実際に債務上限を引き上げなかった例は少なく、仮に一時的にお役所の閉鎖などが起こっても経済に影響を与える例はなかったと言えます。
日本人投資家が米国債を買うのは、米国政府の返済リスクが低いことで元本を保全しつつ、日本より高い利回りを享受したいという理由でしょう。この点では今後の金利動向や格付け変化をひどく気にする必要はないと思います。
しかし、債券の元本保全とは別に、円建て投資家には為替リスクがあります。為替の変動率は大きいので、日本の金利に比べて米国がかなり高い場合には目的に沿った投資成果があるのですが、大きく円高になるタイミングではあまり気分が良くないかもしれません。
為替の変動を抑える為替ヘッジ付きの米国債商品もあります。ヘッジコストがいま高くて利回りが低下するので、ヘッジコストが将来的に下がってきたらこのような商品が多く出回ってくるかもしれません。ヘッジコストを正確に知ろうとすると難しいです。おおまかにいうと、ヘッジして為替の影響がなくなりかつ円債より高い利回りを確定できるというフリーランチは、あるとしても一時的で完全に保証されるわけではないということです。ヘッジ付き外債よりも円債を持っていた方がよかったということになりかねないリスクがあります。
先進国の国債は日本より十分高い利回りを持っている場合、元本保全を期待しながら日本の債券を持つよりも高いリターンが期待できます。ただし、ヘッジの有無にかかわらず、程度は違えどもリスクはあることを知っておきましょう。
この記事に関連する日興アセットのETF
米国債券に投資ができるETF
1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) (愛称:上場米債(為替ヘッジなし))1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) (愛称:上場米債(為替ヘッジあり))

<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。