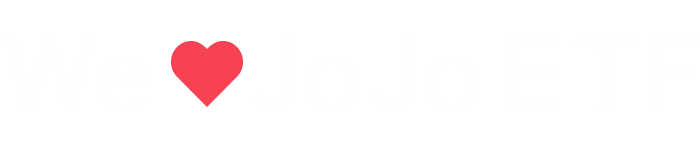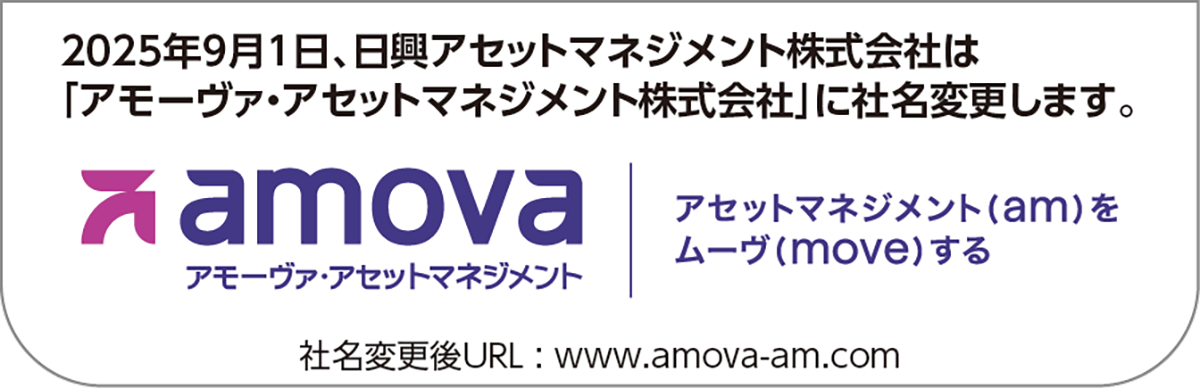- 2023年11月6日
vol.45 投資の資産配分を考えるときに大切なこと
資産配分のルールを決める前に、まずは投資のゴールを決めよう
投資の資産配分にはかっちりとした理論はありません。資産単位で最適な配分を考える理由は、資産ごとに運用のエキスパートが存在するからであって、現実の市場環境に従った方法でしかないのです。
市場全体の適切な配分を信じてそれに合わせる「理論」がありますが、個々の投資家はひとりずつそれぞれのリスク許容度があるのですから、個人としては自分がどんなリスクを想定して許容しながら、どのくらいのリターンを何年くらいで実現するかという問題を先に考える必要があるのです。つまり、大切なのは『 投資のゴール(目的)』をまず決めることです。ここから資産配分の計画について少し考えを進めることができます。

誰でも、資産配分の見直し(リバランス)は必要?
投資のゴールを決めた後、それを実現させるための資産配分を考える必要があります。投資後は、当初の資産配分を維持するための資産配分の見直し(リバランス)が通常必要と考えます。
多くの場合、投資のゴールは、例えば将来ちょっとしたところに旅行したい、音楽やスポーツを楽しみたい、孫に小遣いをあげたいなどさまざまではあるものの、ゴール自体は長期間あまり変化しないでしょう。そうであれば、資産配分は「放置」ではなく、「リスクを一定にする」必要があるのです。
若年層や現役層などの積み立て世代で、株式と債券をばらばらに積み立てている場合、株だけ価格が上がれば株を買う額を減らすなど買い付け額の調整ができます。しかし、なぜそうするのかは知っておく必要があります。
取り崩し世代は、資産評価額が上がった金融商品から取り崩すか、全体から同じ比率(定率)で取り崩すかなどを考える必要があります。
アベノミクス相場(2012年11月14日~2020年8月28日)では、日経平均は約8,000円から24,000円と3倍に上昇しました。その場合、株式の保有額が3倍になっています。一見この勢いを保っていてもよさそうに感じますが、リスクも3倍になっていると考えるべきでしょう。そして、次の2年は下落相場かもしれない。そのとき、リスクの取り過ぎだと気づくことになります。この場合、リスクを一定にするための売買が求められます。
投資のゴールとリスク許容度が一定期間同じであると考える限り、本来できるだけ頻繁にリバランスをする必要があります。ところが、株式と債券の売買にも通常手数料がかかります。その場合、長期的にできるだけコストをかけずに売買や保有をするルールを持っておけば心配は減るでしょう。リバランスのタイミングはそれ自体が研究対象になるほど複雑なので、投資商品自体をシンプルにしておくことがいいのではと考えています。
売買コストや商品の仕組みを気にしながら資産運用を ~神山解説
投資のコア部分については、リスクを一定の幅に自動的に維持してくれる「バランス型」ファンド*を基礎的な部分として持つことが本来は簡単で適切でしょう。ファンドとして大きな残高であることで売買コストを引き下げることができます。
*複数の資産や市場にバランスがよいと考えられる比率で投資する投資信託
バランス型で、債券の割合を多いものを選ぶかどうかは、もともとのリスクの許容度で考える必要があります。 積み立て世代は、シンプルに、自分のリスクの許容度に合ったバランス型ファンドで毎月積み立てていけば、リバランスなど細かいことを考える必要がなくなり、自動で積み立てる趣旨に合致しているでしょう。

取り崩し世代は、積み立てた資産の取り崩しが始まるため、取り崩した残りの投資がリターンを生み出して、できるだけ取り崩しの資産への影響をカバーすることを目的としていると考えられます。保有資産の定額(毎月●万円など)を取り崩すか、定率(投資額の▲%など)で取り崩すかの選択があります。これも投資家自身が受取年金の額と生活水準などから考えておく必要があります。
取り崩し世代は、分配金が生活資金の一部となる可能性が高いため、REIT(リート、不動産投資信託)や高配当株式投信などを保有することが合理的であると考えます。これらは分配金を加味した場合、成長志向の株式投信よりも値動きの上下動が小さくなる傾向にあるので、リバランスの頻度は減らせるかもしれません。引退していれば、いろいろと考えを巡らせる時間があると期待します。
複雑な仕組みを持って、損失を抑えながら分配金を増やす工夫をしたファンドもあります。取り崩し世代には有効なケースもないとは言えませんが、オプションの売買で期待リターンが下がっているケースなども想定され、よほど中身の理解に自信があるときの保有のみにしてほしいです。
このようなファンドは、積み立て世代のゴールがこの仕組みに合致する可能性はほとんどないと言えますので、保有にはくれぐれも自分のゴールとの相性を検討してください。
この記事に関連する日興アセットのETF
リートに分散投資ができるETF
1345 - 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 (愛称:上場Jリート)1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(愛称:上場アジアリート)
1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(愛称:上場Aリート)
2552 - 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) (愛称:上場Jリート(ミニ))
2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート (愛称:上場ESGリート)
高配当株に分散投資ができるETF
1399 - 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ (愛称:上場高配当低ボラティリティ)1698 - 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(愛称:上場高配当)

<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。