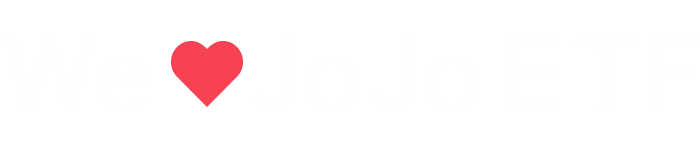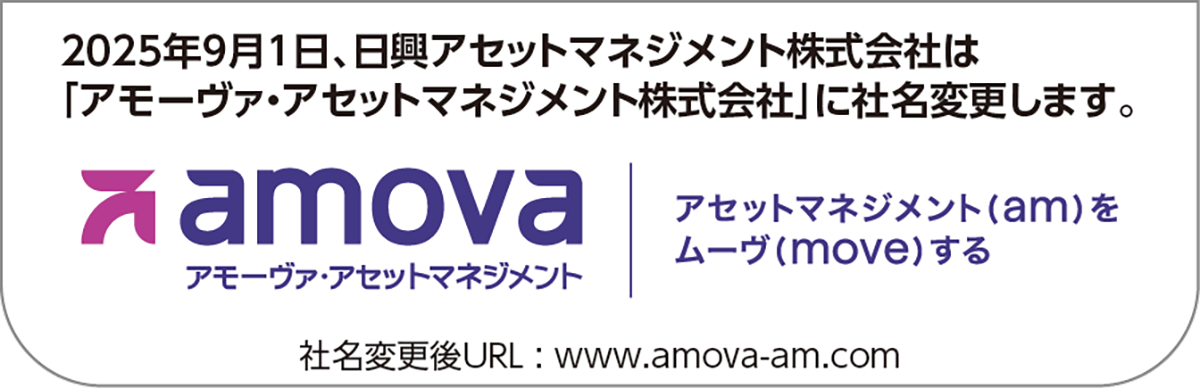- 2024年1月30日
vol.47 インフレヘッジにJリート投資は有効?
Jリートは金利の上昇に弱いのか?
Jリート(日本の不動産投資信託)は、多くの場合オフィスビルなどの資産の半分程度は、負債を使って保有しています。ですので、金利上昇は借り入れコストの上昇になります。しかし、だから金利上昇に弱いというのは単純すぎる気がします。金利が上がる理由は通常インフレが予想されるからです。インフレであれば賃料が上がるのでコストを負担しても、分配金を減らさないで済みます。
金利は市場参加者がインフレと見ればすぐに上昇しますが、賃料は契約更新まで変わらないことが多いです。そして、契約更新では過去のインフレ分も上乗せされた賃料になることが多いでしょう。つまりリートは、インフレによる金利上昇のコスト増は後から賃料の上昇で取り戻すと期待できるのです。
リートは長期の投資対象としては「インフレと金利上昇は気にしなくてよい」のです。金利上昇やインフレに強いのでも弱いのでもありません。これを中立と言います。
これから日銀の金融政策が変更され金利が上昇し続ける可能性はありますが、インフレに見合った、あるいはインフレ以下の金利水準である限り、つまり金利コストの上昇があまりに急激で賃料上昇ではカバーできないような普通ではない事態にならない限りは、日銀の政策によって投資方針を変える必要はありません。仮に日銀がインフレを追い越す金利の引き上げをしたとしても、通常は一時的です。金融政策でリートへの長期の投資戦略を変える必要はないと考えます。

人口減少下の日本で、Jリート市場は拡大できる?
人口減少を嘆くことはよいとして、投資戦略を考えるにあたり人口減少を重視することはないと考えます。投資で大事なのは「1人当たり」の売上や利益の成長だからです。1人当たりの利益の改善は、1単位の資本投入当たりのROEとか1株当たり利益の改善とだいたい同じように進みます。一言で言えば「生産性の改善」が投資の視線として最重要です。人口減少でも1人当たりの売上が高くなり、給与が上がり、幸せであれば、投資成果も「よい」のです。
リートはどうでしょうか。リートのよいところは、不動産の投資信託を運用する専門家が努力と工夫をしてくれることです。仮に人口減でオフィスや住宅の需要が小さくなっても、需要がある良い物件に入れ替えていくことができます。不動産市場が小さくなってもリート市場が小さくなる必要はありません。また、米国のように不動産会社の保有物件がどんどんリートに移って、不動産会社が開発に専念する構造に変わるかもしれません。リートは賃料が安定している物件の運営に集中し、地方の空き家は観光用に再開発されるかもしれません。人間の努力と工夫があれば、不動産市場は人口減でも規模を維持する可能性があります。
一方、規模を小さくしていくリートがあっても概念的には問題ありません。物件を手放す一方で分配金を大きくして、資産を減らしていくことができます。仮に国内で投資先が8割など大きく減ってしまうとしても突然起こるわけではないので、順次備えてライトサイジング(適正化)していくことも選択できます。
どんな場合であれ、緩やかな人口減を想定しても、リスクに見合った十分なリターンを上げる可能性は高いです。
不動産市場全体は、金融知識などから遠い個々人の生活の都合などに影響されるので人口減で持ち主の分からない空き家が増えたりしかねないし、制度変更なども必要となりますが、リートについては専門家の運営のもとで(例外は常に起こるのですが)平均的に適切な成果を上げると考えてよいでしょう。

Jリートはインフレ分が目減りしにくく、長期的に分配を期待する投資
~神山解説
長期投資先としてのリートは金利やインフレ率に影響されにくいことをお話ししました。ただし、「インフレと関係ない」ことは「インフレヘッジ」とは違います。
インフレヘッジは、インフレ分と同じだけのリターンを期待できる投資のことです。理論的には短期金利商品はおおむねインフレと同じ程度の金利水準になるので、インフレヘッジ投資と考えられます。ただし、いまの日本や米国のように金融政策で金利をインフレ率より高くしたり(米国)、低くしたり(日本)している場合、ヘッジができません。それゆえ、理論的にはインフレや金利水準から中立である株式やリートに投資するという選択がリーズナブルです。
引退後に潤いのある生活をするための長期投資をするとしましょう。例えばインフレを取り返しさらにリスクを取る報酬としてインフレ率+3%程度を目標とするとしておきましょう。この場合、株式やリートを保有すれば、インフレは企業の売上や不動産の賃料収入で中立にすることができます。
それに加えて、株式やリートへの投資はリスクの報酬として追加のリターンが獲得できると想定します(そうでなければ、みんなわざわざ投資しませんよね)。必ずそうなると保証はできないものの、余裕資金を潤いのある生活に使うのであれば投資する価値があります。株式やリートだけではリスクも大きくなるので、インフレ+3%程度のリターンを期待するのであれば、貯蓄預金や定期預金と組み合わせることも考えられます。
株式では、経営者が利益の多くを翌年の設備投資に回す傾向にあります。リートでは、賃料収入等をおおむね投資家に分配金として払い出す仕組み*になっています。このため、リートは分配金を含めて考えると、株式よりリスクが小さい傾向にあります。
また、株式との値動きも異なりますので、分散投資の対象として考えることができます。また、テクノロジー企業などのような成長株とリートの相関は低いことが多いでしょう。リートは性質がよく分からないという方も多いのですが、分散投資の対象として優れていると思います。
*J-REITは、収益の90%超を分配するなどの要件を満たすと、法人税が課税されず分配金が出せる特徴があります。この記事に関連する日興アセットのETF
Jリートに分散投資ができるETF
1345 - 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 (愛称:上場Jリート)2552 - 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) (愛称:上場Jリート(ミニ))
2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(愛称:上場ESGリート)

<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。