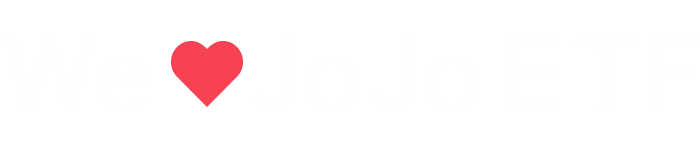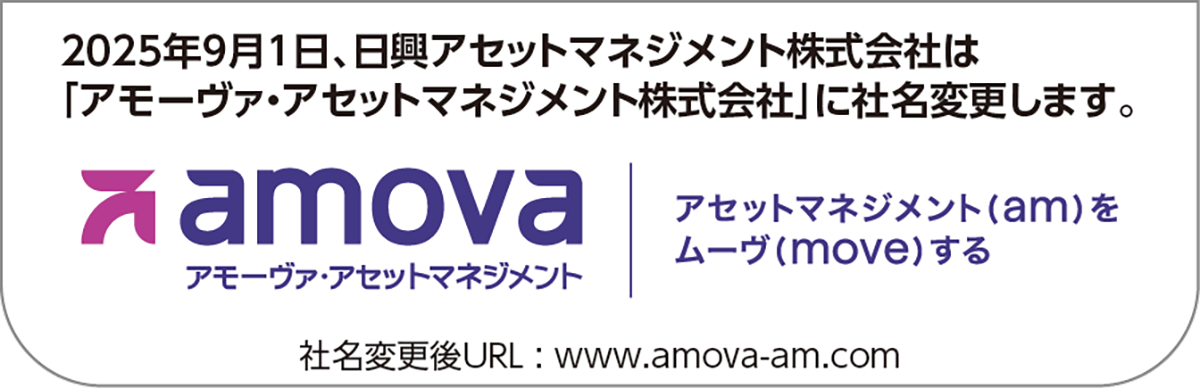- 2024年7月22日
vol.53 米ドル円の為替レート、今後どう動くか
円安はどうして続いているの?
円安が進行する理由はさまざまな説明があり、時期によってその要因も変わっているとも言えます。それゆえ予想がとても難しいです。さらに、為替レートは株式と違って人間の努力と工夫で成長してくような背景もありません。上記を前提に、難しいなりに円安の理由を説明してみます。
2020年終わりに103円台であった米ドル円が、2022年には150円の円安になりました。いまや150円台後半が定着したように見えます。振り返ると、円安が目立ってきたのはなんといってもコロナ禍の渦中です。私は130円を超える米ドル高円安は、コロナ禍の一時的な行動制限による供給不足や各国政府の財政出動の結果に関わっているとみており、その意味で長く続くものではないと考えます。世界経済が正常化すれば、数年かけて100円から110円の範囲に戻ってもおかしくありません。
コロナ禍が米ドル高円安につながった理由は、日米のインフレ格差です。まずコロナ禍は世界的に行動制限でモノ不足となりました。これは日米それほど変わりないことです。しかし、米国ではモノ不足がすぐにインフレにつながりました。この説明も諸説ありますが、米国は日本に比べればもともとインフレ率が高いので、人々がすぐにインフレが強まると予想したから、と考えられます。最初は物理的というより心理的なものでした。
物理的な差になったのは、政府の財政出動の格差です。トランプ大統領(当時)は、各家庭に補助金を配る、失業手当を上乗せするなどを急激かつ多額に行いました。バイデン大統領も追加しました。日本で1人10万円が支給された頃の話です。
米国では日本よりかなり多くかつ素早く支援を行いました。つまりモノを買うお金をたくさん配った米国は、インフレも急激に進むことになります。貯蓄がなければ買い控え、景気悪化につながるところを、政府支出が家計を通じて消費に回り、インフレにつながったことになります。さらに米国では、この消費の集中がさらなる人手不足と賃金の上昇につながります。貯蓄ならいつか消費してなくなりインフレを支えられなくなりますが、賃金上昇が続くと家計にお金が残るので、さらに消費とインフレが続くことになります。FRBは当初貯蓄の取り崩しならインフレは一時的とみていたようです。金利引き上げに出遅れたので、かなり焦って急激に政策金利を引き上げることになってしまいました。

日本は、ごく単純化すれば米国に比べて1人当たりの政府支出が少なく、インフレは相対的に軽いものとなり、日銀はインフレになっても金融緩和を続け、金利の引き上げはごく最近のことになりました。
お金は金利が高い方に流れやすいです。インフレに対応して政策的に金利を高くした米国で預金をすれば金利は5%以上になる一方、日本ではマイナス金利が続いていたので預金ではほとんどゼロ金利でした。円を売ってドルを買い預金しようとする投資家は増えるでしょう。こうして、コロナ禍に端を発したインフレ格差ひいては金利格差が、円に対して米ドルを高くしたと考えられます。
さて、これからは、コロナ禍からの正常化が日米両方で進むとみています。米国のインフレ率はすでに3%以下に低下してきました。目標は2%なのでまだすぐに大きく金利を引き下げることはできそうにないのですが、米国FRB(連邦準備銀行)は引き下げのタイミングを狙っているようです。一方日銀は、やはり目標である2%にインフレが落ち着いてくるとみれば金利をゼロからプラスにする、いわゆる「金利のある世界」に導こうとするでしょう。これはリーマンショック以来の日本経済の金利面での正常化(各国政府のコロナ支援金のおかげですが)を意味しています。米国が金利を下げ、日本が金利を上げれば、米ドルは低下、日本円は高くなるはずです。
ではいつごろそうなるか?これが難しいのですが、米国FRBがいよいよインフレの落ち着きに自信を持つために、インフレ再燃リスクを感じさせる4%台の賃金上昇率が3%台前半に行くときに利下げを始めるかもしれません。FRBが継続的に利下げをしそうだと市場参加者が思い始めれば、ドル売りが始まると思われます。
一方で日銀は日本の賃金上昇率が高まった証拠を待っているように思います。ベースアップ率が予想以上に高いことが確かになってきました。ただし、これまで日本ではインフレ率より賃金上昇率が低い状態が続いて消費が改善してきませんでした。今年後半についに賃金上昇率がインフレ率を一時的にせよ追い抜くことで、いよいよ持続的な賃金上昇とインフレの安定が期待できる状態になるかもしれません。日銀の利上げが続くと市場参加者が期待すれば、やはり米ドル安円高の要因となります。
米ドル円の為替レートはどうやって決まる?
為替レートはどう決まるのかも、時期によってその要因が変わるなどがあり、とても難しいということを前提としつつも、為替の決定について説明します。
まずそもそも論ですが、為替は物と物とを交換するレートです。有名な『マクドナルド平価説』では、アメリカでビッグマックを食べても日本で食べても同じですから、価値は同じはずと考えます。同じものがアメリカで2ドル、日本で200円なら1ドル100円のはずです。経済全体の交換比率はビッグマックだけでは決まりませんが、同じものには同じ価値があるという思想が為替を決定する基本観です。

ところが、上段では円安について、インフレ格差と金利差で説明してきました。実は、為替レートは物の交換比率と言いましたが、物の値段が毎日変わっている世界ではどうでしょうか。インフレが含まれるのではないかということになります。ビッグマックが米国では2ドルのまま、日本では明日にも200円から250円に上昇するのであれば、それを見越して1ドル125円になりそうなものです。物価が基本であれば、先回りしたい金融取引ではインフレを気にすることになります。
では、インフレと金利の関係とはなんでしょうか。インフレと金利はだいたい同じように動くべきです。例えば、今日200円誰かに貸したとしましょう。明日には物価が上昇しビッグマックは250円になるとしましょう。いま200円貸して明日返してもらうと、もう200円で同じビッグマックが買えません。だから今日200円貸すなら明日250円返してほしい。そうでないなら貸さないで今日のうちにビッグマックを食べたほうがましです。「お金を貸す人は、受取金利で物価上昇をカバーする」と考えるのが分かりやすいです。そうでなければお金の貸し借りはできないというわけです。
為替に金利が関わってくる理由は、上述したように、金利が高い方に預金する方が得だからです。インフレ率が高いと金利も上昇しますので、その通貨に交換して預金しようとするでしょう。インフレが強く金利が高い国の通貨は強くなります。ここでは、先ほどの物と物との交換という考えが少し進化して、物の値段の変化であるインフレを背景とした、金利と金利の交換という意味が出てきます。
とりあえずこのような説明となりましたが、いまの状況の分析のために、短期金利を中央銀行が動かしているという別の問題を考えないといけません。いまFRBはインフレを押さえ込もうと意図的にFRBがインフレ率以上に金利を高くしています。日銀はデフレに戻らないためにも、金利をインフレ率に合わせて上げずに低めに維持しています。
為替水準はこのため現実のインフレ率格差以上に中央銀行の政策の差に依存することがあります。今は特にこの傾向が強いです。インフレ率の今後について介入したい中央銀行がどのくらい臆病かあるいは積極的かといった判断が短期的には為替を見るために大事になります。
為替レートと海外資産への投資 ~神山解説
そもそも論である同じものの値段の比率や、インフレ率の長期的な格差などから考える為替レートは、長期的に戻っていく場所として考えられ、中央銀行の金利政策の差は短期的なものと想定してよいでしょう。
長期投資の観点では、為替は当てるものではなく中立とみなします。株式は人間の努力や工夫が価値となると期待できますが、為替レートはそのような努力への投資対象ではないので、大きくぶれるものの本質はその国の株式を中心とした経済の成長に投資しているとみなすのがいいでしょう。ただし、新興国であれば経済構造の変化(農業中心から工業へ)で為替が増価することがあるとされていますので、例外的に経済構造の変化に投資するとみなしてもよさそうです。しかし、先進国同士の通貨については、それぞれの潜在的成長率が同じ程度であるかぎり、投資と考えるのは難しいです。
また、金利差も実は長く続くとは言えません。インフレ率が高い国に低い国から投資資金が流入すると、いずれ生産が増えモノ不足が減りインフレが落ち着く可能性が高まります。つまり高金利とインフレは基本的にサイクルであるとみることができ、高金利の国で預金すると、だんだん金利が低下して為替も弱くなり、高金利分を為替の弱まりで相殺してしまうかもしれません。実際にはきれいに収れんしませんので金利が高い国への投資は結果として利回りも高いという投資の経験則はあるのですが、本来は高金利と通貨高はいつまでも続かないとみておくべきだと思います。
海外資産への投資はいつも為替に頭を悩まされます。なんでもヘッジすればいいとの意見もありますが、ヘッジコストがかかり、特に日本から米国に投資する場合、米国の短期金利が長期金利より高い今のような状態でのヘッジコストはとても高くなってしまいます。しかも、投資を始める時にはヘッジコストが安くても状況が変わってあとからとても投資に見合わないほど高くなるリスクもあります。ヘッジと言ってもそれほど簡単ではありません。
海外資産への投資は分散投資の観点からお勧めします。長期投資であればあまり為替を気にせず、米ドル、日本円、ユーロやポンドを含む幅広い投資対象に分散することで特定地域の為替リスクをできるだけ避けるようにするのが良いと思います。そして、インフレ率などを予想して動く金利・為替市場を予測して賭けていく投資はお勧めしません。為替をリターンの源泉と捉えるとトレーディング的な投機になりやすいので(それが目的なら構いませんが)、投資とは区別しておきたいところです。
この記事に関連する日興アセットのETF
米国債に投資ができるETF
2093 - 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) (愛称:上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし))1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) (愛称:上場米債(為替ヘッジなし))
1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) (愛称:上場米債(為替ヘッジあり))
世界の国債に投資ができるETF
1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(愛称:上場新興国債)1677 - 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(愛称:上場外債)
世界の株式に投資ができるETF
1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (愛称:上場MSCI世界株)1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) (愛称:上場MSCIコクサイ株)
1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) (愛称:上場MSCIエマージング株)
※上記銘柄(1677 愛称:上場外債 を除く)は新しいNISA制度の「成長投資枠」の対象ETFです。

<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。