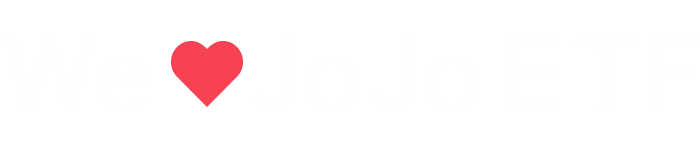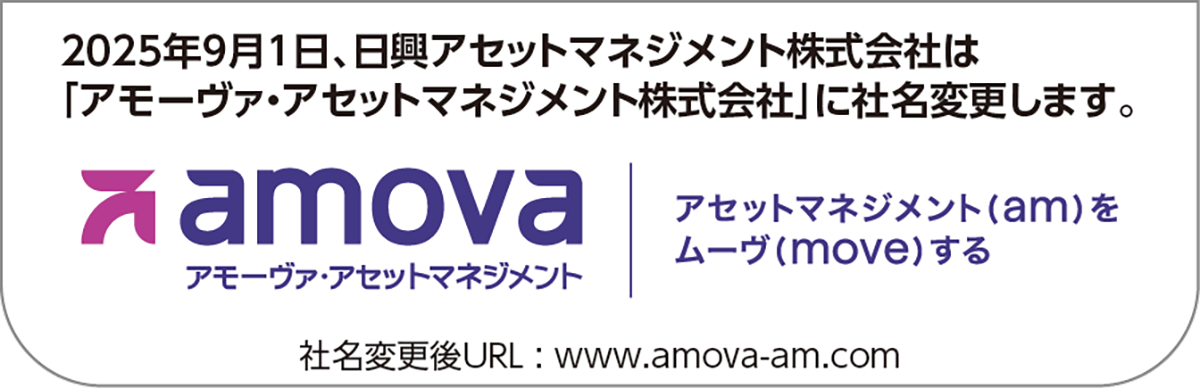- 2024年10月1日
vol.55 自社株買いは投資家にどんな意味をもつの?
そもそも株主還元とは何だろう?
株主還元とは株式の発行会社が株主に報いることで、自社株買いもその一つです。会社が自分の会社の株を買うので、株価が上がって良いことに思えます。そもそも自社株買いとは何なのか、きちんと分かっている人はそう多くはないのではないでしょうか。配当と似ているのですが、なぜ自社株買いをするのか、投資家としては喜ぶべきか悲しむべきか考えてみたいと思います。
まず、投資家は株主ですから、株主還元を喜ぶでしょう。株主は配当などの還元によりリターン(収益率)が上がります。株価の上昇によってリターンが上がりますが、株価は将来の配当が増えることを期待して上がるので、配当が大事なことに変わりはありません。では、自社株買い、配当といった株主還元とはどのようにして行われるのでしょうか?
まず、良い知らせです。会社にお金が余っていると、株主に還元することが適切です。株主はリスクを取って株式を保有するので、そのリターンがまったくないのはおかしいし、そもそも預金のような安全な資産ではなくわざわざ株式を保有するのですから、ある程度の高いリターンを期待しています。会社は、株式で集めたお金で設備も買ってモノを作り販売して利益を得ますから、その利益を株主に還元するわけです。
次に、悪い知らせです。会社に「お金が余っている」のはそれほど良い知らせではありません。そもそも会社は株主からのお金を元手に銀行などからお金も借りて、将来稼げる事業に乗り出し、成果を出すことが期待されています。儲かったお金を還元するということは、「成長機会が見つからない」ことを意味していて、成長しない分を還元しなければならない、ということになります。成長しない会社は悪いということはないですが、その分適切に配分しないと株主に責任を果たせないことになります。

こう考えると、株主は「適切な」株主還元を求め、そうなっているか監視することが求められます。株主還元は、会社が利益は十分あるが成長期待が目先見当たらない(いわゆる成熟産業の会社など)場合、しばしば行われることになります。配当であれ自社株買いであれ、そこで投じた資金は、そもそも利益として会社が取り入れ、次の成長分野への投資に使われない資金です。
ですから、株主還元は、ROE(自己資本利益率)を一定にさせるように決まるはずのものです(もし面倒くさい話だと思ったら読み飛ばしてください)。今期の利益/資本=ROEだとすると、今期の利益のうち、分配しなかった額が翌期の資本に回るので、もし利益が増えないとROEは低下します(分母が増えて分子が同じだから)。これは投じた資本の稼ぎが下がることになり、無駄な金を持っているという悪いシグナルになります。そうならない程度に適切に株主還元(配当や自社株買い)をすれば、翌期の資本を増やさないので「資本効率が維持される」ことになります。また、仮にお金が余っていて放置している資本効率の悪い会社であれば、たくさん株主還元をすることで資本(分母)が小さくなってROEが改善します。
というわけで、まず会社は資本効率を適切に(適切とはどの程度かというと難しいのですが、分かりやすい例では、同業の最も良い効率の会社と同じ程度に)維持するために株主還元の額を決めるのが良いのでしょう。
ROEが上昇すると株価が上昇しやすいです。仮に1株当たり利益が上昇しなくても、還元で資本効率が改善しROEが上昇すると、しばしば利益が同じでもPER(株価収益率)が上昇して株価が上がります。これは、株式市場が、その会社の資本効率が良くなる、つまり投入した資金に対して稼ぎが良くなったと理解するからです。逆に日本には適切な程度のROEになるよう使わない資金を還元しない上場企業が多く、資金が無駄に資本として滞留してしまい、日本経済の効率の悪さの一つとなっているのです。
自社株買いと配当の違い(実は同じです・・・)
では、株主還元の方法に、自社株買いと配当の二つがあるのはなぜでしょうか、どちらが株主に良いのでしょうか? 実は本質的にはどちらも同じです。
米国では株主にとって配当より自社株買いのほうが目先の税金が安いなどがあって、自社株買いが大流行しました。日本では原理的には(場合によりますが原則として)どちらも税率が同じですので、株主はどちらかを気にしなくてよいです(将来は、日本でも配当やキャピタルゲインの税率が変わる可能性があるので、その点では今後は変わってくるかもしれませんが)。
現状の違いとしては、自社株買いは、会社の経営者が自由にタイミングを決めやすく一時的なもの、配当は一度増配するとなかなか下げられないので、経営者に継続の自信が強い場合に行うと区別できます。日本は特に減配(配当を減らす)が起きるとまるでクレジット・イベント(借金をしていて利息を払わない、遅延する)などと同じように扱っていた時期がありました。おそらく銀行が株主でもあった時期が長かったために今でもその空気感が残っていて、海外に比べて、利益が出たから素直に増配する、うまくないときには減配するといった行動がとりにくいのだと思われます。そこで、一時的に余った資金を株主に返すときには自社株買い、新規事業が軌道に乗るなどして、将来に自信があるときには増配、という選択が多くなっています。
ところで、大量の資金を株主に一時的に還元したいと思った会社があっても、株式市場の流動性が低く、思ったように還元できない会社もあります。そういう会社は、例えば「創立何周年記念」などの名目で記念配当など一時的な増配を行うこともできます。記念配当は必ず流動性が低い会社だという意味ではありませんが、自社株買いがしにくい会社もあるということ、記念配当や特別配当などとして配当をもっと機動的に変更できると市場参加者みなが理解することが望ましいです。というのは、会社が減配をしたくないということに拘泥したり、自社株買いをするには株式の流動性が低いケースがあることなどを考えると、適切な還元と資本効率の改善ができなくなるからです。
日本企業の資本効率が変わる時は今 ~神山解説
現在、日本の上場企業(つまり大企業)の半分が、実質的に負債がない状態になっています。一見良いことのように見えますが、稼いだ利益を借金の返済に使うくらいしかなかったケースが多く、負債がなくなるだけならまだしも、多くの会社で余った現金が増え続ける状態になっています。
また、余剰人員を抱えて「やらなくてもいい事業」に進出していたり、成長分野や新規事業への進出に使わず、不動産保有で滞留させたりしていることもあります。これまでこのような経営常識では、それらが悪いことではなく「規模と安定」を守ることとして評価されていました。しかし、日本の人口減少など厳しい環境が来るとすれば、この状態は変わらねばなりませんし、変わることができるはずです。「効率と成長」がこれからのキーワードです。

多くの日本の大企業は、
① 世界の同業他社のROEになることを目標として、
② 利益として獲得した資金を適切に新規事業や成長分野に投入し、
③ 世界の強豪のROEになるように適切な株主還元をする、ことで、高い効率と成長が期待できる状態に変身できます。
その意味で日本株のポテンシャルは大きいと言えます。②はデフレ下の日本では難しかったかもしれませんが、いまや人手不足、設備不足など、変革には絶好の機会が訪れています。多くの日本企業が株主の視線を意識した適切な成長機会への投資と資本効率の改善のための株主還元には、価値観や考え方の変化が必要です。
いわゆる東証改革で上場企業に高いPBR(株価純資産倍率)(ひいてはROE)を求めるなどで変革の可能性は高まっていますが、十分大きな動きになるかは、まだ確実とは言えないです。だからこそ千載一遇の機会を得た日本企業が「効率と成長」に向かって変わるときにさらに株価上昇の余地が残されています。
この記事に関連する日興アセットのETF
日本株に分散投資できるETF
1308 - 上場インデックスファンドTOPIX (愛称:上場TOPIX)1330 - 上場インデックスファンド225 (愛称:上場225)
1399 - 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ (愛称:上場高配当低ボラティリティ)
1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (愛称:上場日本経済貢献)
1592 - 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 (愛称:上場JPX日経400)
1698 - 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) (愛称:上場高配当)
213A - 上場インデックスファンド日経半導体株 (愛称:上場日経半導体)
※上記銘柄は新しいNISA制度の「成長投資枠」の対象ETFです。

<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。