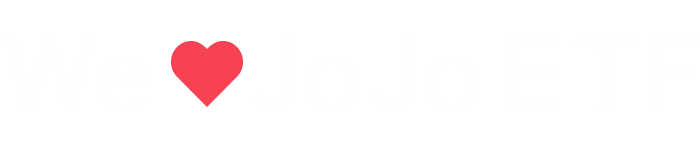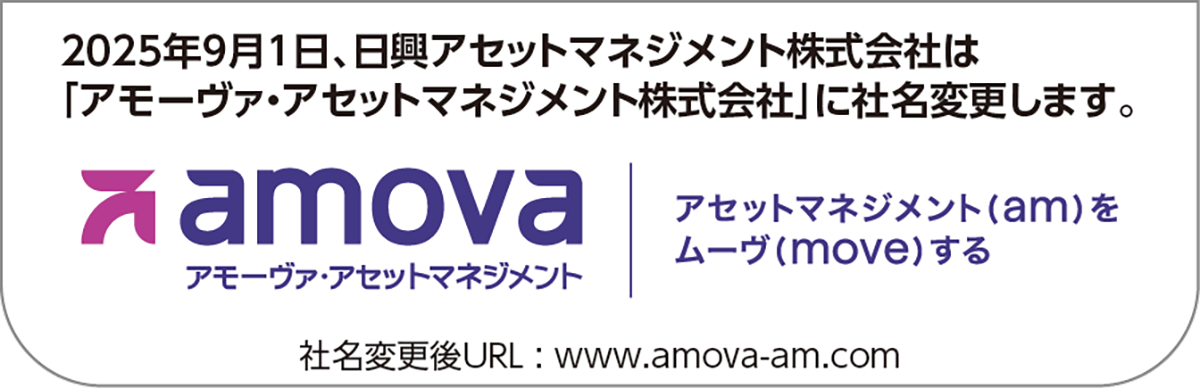- 2024年10月29日
vol.56 米国大統領選2024での株価の行方
トランプ氏とハリス氏、大統領選によるマーケットへの影響をどう見る?
アメリカでは民主党と共和党の二大政党制が定着していて、大統領選は実質的に両党が指名した候補の一騎打ちとなります。今年の大統領選では、共和党がトランプ氏、民主党がハリス氏を候補として選んでいます。株式市場が注目するのは、大統領の経済政策です。
例えば、共和党のトランプ氏は、中国からの輸入品に高関税を課し、他の国からの輸入品にも関税を引き上げて、米国内での生産を保護したいとしています。これだけ取り出すといかにも消費の悪化につながりそうですが、一方で企業減税や補助金を出す可能性が高く、全体として政府支出は増加の可能性があるとされています。
民主党のハリス氏は現在副大統領ですから、現状を破壊するような政策は考えられませんが、バイデン氏が実現できなかった富裕層増税、中間層減税を狙っているとされます。これも全体としては減税が多ければ経済拡大となりますが、とんとんとなれば経済全体への影響は小さいです。
つまり、どちらが選ばれても、GDPの成長を止めるような政策を取るとは考えにくいわけです。次期大統領は、今後の選挙を考慮して政治的なパワーを維持したいでしょうから、財政拡大の誘惑が強いでしょう。したがって、誰が大統領になってもGDPの成長にはそれほど影響がないとみています。
そして、大統領選の市場への影響は短期と長期に分けて考えられます。
長期投資の観点から見ると、GDP水準が変わらなければ指数水準も変わらないと考えられるため、次の大統領によって投資先を変更する必要はないでしょう。
ただし、短期的には、政策の種類が違うので、良いセクターや銘柄と好ましくないセクターや銘柄が出る可能性はあります。トランプ氏であれば、CO2排出にこだわりが少ないので、石油パイプラインの認可を進めるなどして、エネルギー産業に目先メリットがあるかもしれません。ハリス氏であれば、逆にCO2排出を減らすエネルギー源へ投資する企業が有利かもしれません。
もっともこのような短期的な見方も、同時に行われる議会選挙結果で変わります。大統領と同じ政党が下院の多数派となれば、政策実行能力が高まります。下院は税金を含め予算を決めるからです。下院と大統領の政党が異なりねじれた場合、大統領が大統領権限で中国からの輸入品の関税引き上げを決めても、下院が企業や個人の減税を拒否すれば、大統領の政策が現実には撤回されることもあり得ます。政治的なやりとりは予想しにくく、短期的なポジションを取ることはそれほど簡単ではありません。
結論としては、大統領によってセクターや銘柄を調整しても良いのですが、せいぜい来年1月の大統領の政策発表あたりで一山超えてしまうでしょう。その後は、例えば半導体関連の収益の推移などのほうが株式市場にとって重要になります。大統領選のマーケットへの影響は、単にボラティリティが高まるという点を除くと、一般に長期的な影響は小さいと考えられます。

大統領選に投資で立ち向かうことは投機
資産形成の視点では、大統領選を材料に投資することはお勧めしません。ボラティリティが高まり、大統領に決まった人の発言に揺さぶられ、毎日激しく上下動することがあります。州によって選挙結果に疑いがあるなどのニュースにさいなまれることもあります。
マーケットのブレを利用して取引するヘッジファンドなどプロ投資家もいますが、老後の潤いのある生活のための投資にはなりません。大統領選の結果を個人が投機的売買のお楽しみに使うことは否定しませんが、そう割り切っておいてください。投資で立ち向かう必要はないでしょう。
そして、大統領選の勝敗と政策比較は一時的な話題となるものの、内容がその通りに実現するとは限りません。さらに、実現しても、経済サイクルのタイミングを変えたりする可能性はありますが、GDPや株価指数を長期的に動かす原動力となることはまれです。重要となる長期的な経済の変化には、通常、民間企業の自助努力による生産性の変化がカギとなります。政府は企業が生み出した付加価値の分配先を調整したりはしますが、政策が価値を生み出すことはあまりないのです。米国経済と市場はそれほどまでに成熟していると言えます。
米国のインフレ度合いに注目 ~神山解説
大統領選でも話題になるインフレについて、トランプ氏は、インフレはバイデン大統領のせいであると主張しています。しかし、そもそもトランプ前大統領がコロナ禍という特殊事情に対する対策として大規模な財政出動をしたことは、その後のインフレの原因となっているとも言えます。問題は、インフレが国民の心理に悪影響を及ぼしているので、どちらの大統領も思ったほど財政拡大ができない可能性があることです。実際、バイデン大統領が公約を積み残している理由は、財政拡大でインフレを悪化させたくないという判断が含まれているようです。

逆に、労働者不足による賃金上昇とインフレの持続を恐れて、それだけではないでしょうが、バイデン大統領の時代に移民が大幅に増えました。今後どちらが大統領になっても社会問題としての不法移民を大幅に減らすことが想定されており、これが労働者不足、賃金上昇によるインフレ長期化につながる恐れがあります。
経済次第で人の動きが変わるので、移民政策だけで労働力需給を判断することは難しいのですが、今後の大統領候補の発言に注目が集まるほか、新大統領の政策次第でインフレの恐怖が生まれる可能性はあります。実際にどうなるかよりもそうなる恐れが市場を動かしがちです。大統領選と政策にまつわる話は短期的な問題であって、長期的にはそれほど重要とは見ていませんが、シナリオについては下記のようにみています。
メイン・シナリオでは、大統領が誰であれ、移民政策がどうであれ、コロナ禍に始まったインフレはいったん収まり、FRB(米連邦準備銀行)の政策金利も通常状態に時間をかけて戻っていくとみています。
しかし、リスク・シナリオとしては、急激な移民政策の変化で一部の労働市場が逼迫し、賃金が急上昇してインフレ懸念が強まり、FRBが利上げを行い、結果として経済が悪化する可能性も否定できません。実際には、経済成長率の鈍化やソフトランディングによって労働者の流入が減少し、ちょうど良いバランスが取れる可能性も考えられますが、そうなってみないと分からないとは言えます。
メイン・シナリオはインフレ鈍化、政策金利低下です。ただし、長期金利はすでにかなり先回りして低下していますので、さらなる金利低下は限定的と考えられるでしょう。短期金利の低下は、円高圧力にもなりますので、米国株が良いパフォーマンスを示しても、円高によって日本円での評価額が低下することも将来的にあり得ます。
この記事に関連する日興アセットのETF
米国株に投資できるETF
<S&P500関連指数に投資できるETF>
2521 - 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり*
2239 - 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍
2240 - 上場インデックスファンドS&P500先物インバース
<NASDAQ100に投資できるETF>
2568 - 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし*2569 - 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり*
<ダウ平均に投資できるETF>
2235 - 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし*2562 - 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり*
※上記の*のついている銘柄は新しいNISA制度の「成長投資枠」の対象ETFです。

<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。