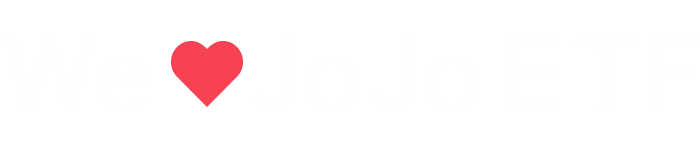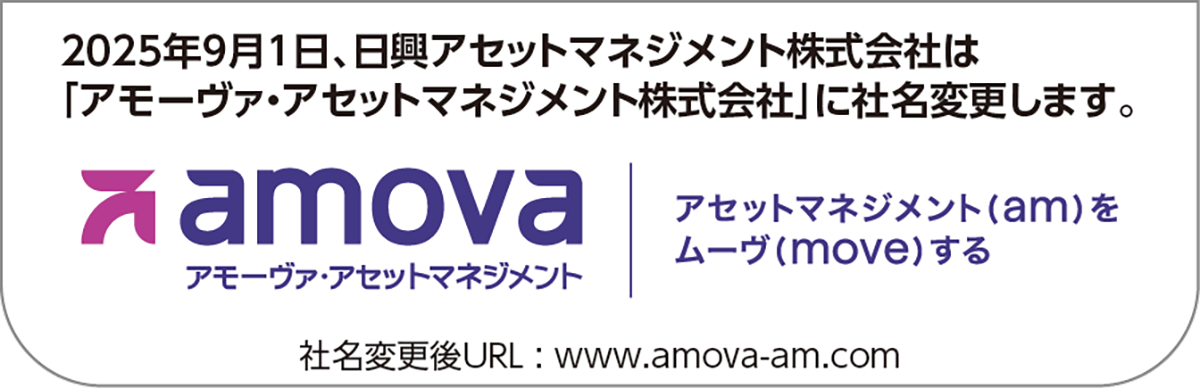- 2024年3月27日
vol.50 ついに日銀の異次元緩和が終了。日本株ETFはいつ売り出すのか。
ETFの買い入れ停止は、投資家にどんな影響があるの?
日本銀行は、2024年3月19日の金融政策決定会合の「金融政策の枠組みの見直しについて(PDF)※日本銀行のサイトに遷移します)」のなかで、『ETFおよびJ-REITについて、新規の買入れを終了する。』と正式に公表しました。
日銀のETF買い入れはこのところ大幅に減っており、株価が下がった日にも買い入れがないことありましたので、日銀の買い入れがないことで日本の株価指数が下がるなどの影響はないでしょう。
そもそも、日銀は日本の株価指数に連動するETFの買い入れを「リスク・プレミアム介入」と名付けていました。アベノミクス(2012年)のころの株価上昇はETF買入れによるなどとの誤解もあったのですが、実際は日経平均のPER(株価収益率)はほとんど上昇しておらず、リスク・プレミアムは低下していません(簡単に言えば、株式のリスク・プレミアムはおおむねPERの逆数のようなものです)。その意味での介入の目的はそもそも大して果たされていません。

しかし、日銀のETFの買い入れは、日本株の株価が下がりにくいかもしれないという心理的な影響を投資家に与えてきたとは言えます。株価指数が下がった日ほどETF買い付け額を増やす時期があったからです。株価が下落する事態になったときに、この効果が期待できないということは頭に置いておいてもいいです。しかし、このような買い付けによる株価へのインパクトは、普通はその日のうちしかもたないようなものです。長期のリターンに影響を与えられたという確かな証拠は見つかりません。
市場の信頼性を高めたJリートの買い入れ
さて、日銀は、Jリート(不動産投資信託)の買い入れも停止しました。Jリートの買い入れもETFと同じでリスク・プレミアム介入と位置付けられていました。Jリートの介入が始まった2010年、日本のリート市場はあまり信頼されていませんでした。不動産会社が開発してうまく売れなかったあまり魅力のない不動産を、自ら設定したリートに持たせるのではないかといった不信感が強かったです。Jリートの分配金利回りは平均6%ほどもありました。これは金利と比べてかなり高い印象でした。介入を経て、Jリートの平均分配金利回りは一時期は3%と、6%の約半分の水準の時期もありました。これは簡単に言えば、介入前と後で価格が2倍程度になったことを意味します。
そのため、リートについては、日銀の介入は、市場の信頼性を高める効果があったとみています。日銀が買い入れるほどまともな市場だという宣伝になったわけです。これは、日銀の意図は別として、リスク・プレミアムの低下となったと言えなくもありません。しかし、このような事態は今後は起こらないとみておくべきです。投資家は、リートには価格上昇ではなく、投資家自身にとって分配金利回りが十分かという観点で投資するべきです。

日銀がマイナス金利を解除することで、金利上昇でリートの金利コストが上がるという懸念も出ています。
しかし、日本経済は設備投資の増大、賃金上昇とインフレ継続の期待が高まっており、これから不動産にとってはチャンスが広がりそうです。心配されたほどのリモート勤務の定着はなさそうで、オフィス拡張の話題も増えてきました。空室率はゆっくりと戻りつつあります。そうなれば、家賃の引き下げよりも、良い物件から家賃の引き上げの話が緩やかに出てくるでしょう。基本的に金利が上がるほどのインフレであれば家賃は上げられるはずです。家賃が上がれば、それに応じて分配金を引き上げることになります。
リートは、インフレで金利が上がるときに、いったん負債のコストが大きくなりますが、例えば契約期間に応じて家賃をインフレ分だけ引き上げます。ですから、一時的に金利負担が増えても、その後は数年分のインフレに当たる引き上げで収益が改善、分配金が引き上げやすくなるのです。ですから、リートはインフレと金利高について長期的には中立(影響がない)と言えます。
日銀が保有する日本株ETFのこれから ~神山解説
ところで、政策変更で日銀が保有するETFを売り出すのではないか、株価が下がるのではないかとの恐れがあるようです。これについて日銀はあまりヒントを出していません。
しかし、これまでの日銀の政策、例えば銀行保有株買い取りの結果として保有していた株式の売却にはずいぶん時間をかけました。現時点は、日銀がETFを市場で売却をし始めるとしても、数年後ではなく、かなり先になると考えます。株式の需給に心理的な安心感がまだ残っていても、売却を始めれば逆の効果がでてしまうからです。仮に、日銀が売却に影響がないと言ってしまえば、そもそも買い入れに大して影響がなかったことも認めることになってしまいかねません。
日銀が株式の大きなリスクを持っていることになるので急いで売るという見方もありますが、すでに大きな評価益を抱えているので、実現損が出るという意味で大きなリスクになるのは、よほど大幅な株価下落の場合だけです。しかもそんな状態で手持ちのETFを日銀が売ることは、これまでの政策を否定することになるので実際には起こらないでしょう。
株価が安定した時期を選んで、信託銀行などに売買を委託し、「上がったら売る」ような方法で、長い時間をかけて売却する、しかも売却開始は何年も先になるとみてよいと思います。
また、一部で日銀がETFを国民に安く譲る、年金に保有してもらうという案も出されています(日銀以外からの案です)。これは政治がリードすれば不可能ではないかもしれません。いまでも銀行保有株式の買い取りで保有した株式の売却では、いわゆる市場外のブロック取引が使われています。ETFも市場ですべて売る必要はないのであって、ETFに含まれる日本株式を、個々の株式に分けて必要に応じて売却することも技術的には可能です。ただしこのような方向での処理があるかどうか、現時点ではまったく分かりません。提案はあっても日銀が検討したようには見えませんし、まだまだこれからの検討課題のひとつというところでしょう。
ひとつ言えることは、日銀が日本株のETFやJリートを買い支えるかどうかよりも、『vol.49 ついに日銀がマイナス金利解除。金利のある世界はどうなる?』で述べたように、日本の経営者が売上げ上昇に自信を持つか、消費者が賃金上昇の継続に自信をもって消費するかのほうが大事ということです。投資家の皆さんは、投資の目的を考えた上で投資対象を定め、投資を続けて行ってほしいと思います。
※当ページは、一部個人の見解を含み、会社としての統一的見解ではないものもあります。
この記事に関連する日興アセットのETF
日銀の買い入れ対象だった日本株のETF
1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(愛称:上場TOPIX)1330 - 上場インデックスファンド225 (愛称:上場225)
1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ) (愛称:上場日経225(ミニ))
1592 - 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 (愛称:上場JPX日経400)
1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (愛称:上場日本経済貢献)
Jリートに投資ができるETF
1345 - 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 (愛称:上場Jリート)2552 - 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) (愛称:上場Jリート(ミニ))
2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート (愛称:上場ESGリート)

<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。