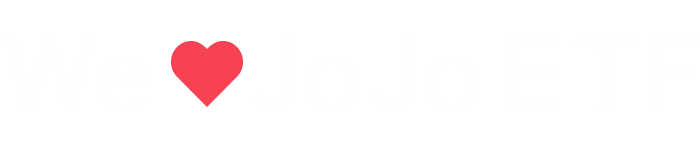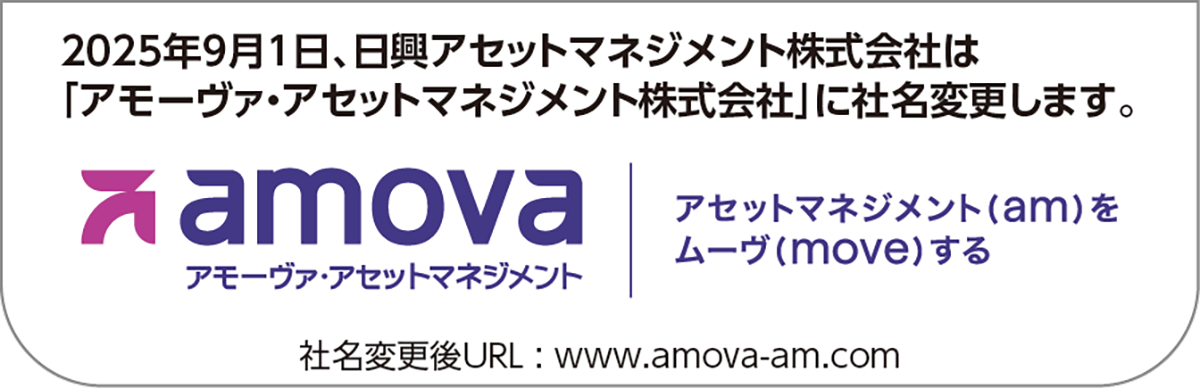- 2025年5月1日
vol.60 インデックス投資商品とのつき合い方
インデックスを選ぶポイントは?
個人投資家が指数(インデックス)に連動する投資商品を選ぶということは、簡単なようで難しいです。指数がいくつもあるからです。
日本市場を代表する株価指数では、日経平均株価とTOPIXが有名ですが、読売333*という指数も現れました。違いの説明はいろいろあるのですが、多くの場合どう計算されるかの説明に終始しています。
その指数にどんな性格があるかを説明してくれる場合もあるものの、どんな人のためにどう役に立つのかという観点ではなかなか説明されていないように思います。ただし、ここで私がどのように役に立つのかを説明することはやはり困難です。人は投資でどのような目的を持つのか、が共通の理解になっていないからです。
インデックスというのは、もともと上場された株式の株価が「全体としては」どう動いたのかを示そうとして発明されました。はじめは単に上場された株価の平均値で良かったのですが、企業が増資をしたり合併したりするとそのことを「調整」した平均値を出すことが結構面倒なことが分かりました。そこで、「ダウ式」というダウさんの方法がもっともよさそうと認知されてニューヨーク・ダウが生まれました。
過去に東証がそのやり方で、東証修正株価平均(東証ダウ平均株価)という指数を作りました。東証ダウは長く使われたのですが、戦後すぐに上場している主要銘柄225銘柄だけを対象にしていたので、市場全体が見えにくい、産業構造変化をとらえにくい、さらに時価総額の大きい銘柄のリターンへの影響が大きいようにすべき(ダウ式では価格の大きい企業の影響が大きい、いわゆる値がさ株)といった問題があり、東証はダウ算出の権利を日本経済新聞に売却し日経ダウとなり、東証はTOPIX(東証株価指数)の算出を始めたのです。日経ダウは、その後日経平均に指数の名前を変えて今に至ります。
TOPIXと日経平均の違いで分かるように、インデックスの違いは「どちらのほうが市場を代表する力が強いか」という議論であって、「投資家のどんな目的に合致するのか」という点はそれほど重要ではありませんでした。
一方、米国では年金運用が重要になってくると、年金基金がアセットマネージャーを雇って、インデックスをベンチマークとして、それを上回る成果を目指して運用する手法が広がりました。この時には、ファイナンス理論に従うことがプルーデント(誠実)であるとの考え方が強まり、運用ベンチマークを適切に選ぶことは、理論(投資可能な証券すべてをカバーするべき)に近い指数を選ぶことを意味するようになりました。日本ではTOPIXがその役割を担う指数として選ばれました。
*「読売株価指数(読売333)の知的財産権およびその他一切の権利は株式会社読売新聞東京本社および野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、株式会社読売新聞東京本社および野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、 読売株価指数(読売333)の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性、適合性および適法性を保証するものではなく、読売株価指数(読売333)を用いて行われる乙およびその関係会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。」なお、読売333に関するデータ利用及び掲載をご検討される場合は、ライセンス代行先であるNFRC(以下問い合わせ先)にお問い合わせください。
---<問い合わせ先>--- 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング(NFRC) インデックス事業部 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 03-6703-3986

その後、なんでもすべて含めるという指数とは別に、外国人投資の比率が決まっている国や銘柄の調整、配当の税金の源泉課税かどうかなど、投資家の種類に対応してMSCIの世界指数などが現れるようになりました。
このように、インデックスはいろいろな経緯を経て様々な種類になったのですが、これが個人投資家向けに設計されているとは言いにくいです。そこで少し無理をして選ぶポイントを考えてみます。
個人投資家の場合、長期投資であれば、セクターや銘柄などいろいろな固有の性格により生み出されるサイクルやノイズ(サイクルもノイズの一種ですが)を気にせず、予想を超える大儲けや大損の可能性を低くし、その地域全体が持つ成長というシグナル度の高いものに投資することが考えられます。 【ご参考】サイクルとノイズとは?
アメリカの場合、アメリカのイノベーションのすごさがあり、欧州や日本で見当たらないマグニフィセント7のような優位性を有する企業に投資したいと思うでしょう。そうであれば、S&P500のように大型株が多くNASDAQ100ほどイノベーションだけに集中しないものでも良いのかもしれません。しかし、もし大きく世界株インデックスに投資している人がアメリカのイノベーション部分を追加で欲しいと思うなら、NASDAQ100を「加える」ことで調整できることもあります。つまり、こんな投資目的ならこの指数というやり方をするために、基本的な指数の性格を自ら知っておく必要があることになるのです。
最も大事なのは、投資家が「アメリカのイノベーションにはいつも参加しておこう」等の投資の目的を持っている必要があるということです。指数は道具でしかないので、投資の目的と指数の性格を合致させることが一番大事と考えています。
指数(インデックス)は、どう設計されるべき?
少し話を変えて、これからの日本株の指数について考えてみます。
これまでしばしば指数の開発で言われてきたのが、「今の指数はなんだか日本のうまくいっていないところをまとめているような気がする」という視点だったと思います。そのため、指数を見直して外国人投資家に日本を見直してもらおうという考えがあるように思いました。しかし、投資の専門家なら「高ROE(自己資本利益率)」を集めた指数が一番良いパフォーマンスとは言えないように、企業の健全な財務体質が、必ずしも株価リターンの高さに直結するわけではないことが知られています。高ROEで流動性が高いから是非お勧めですといった指数が、そうでないTOPIXより、よいパフォーマンスとは限らないのです。
では指数設計がそもそも「パフォーマンスが良いほど良い」のかというのも分かりません。年金運用であればファイナンス理論に近いほど「正しい」と言いやすいのですが、そのつもりで時価総額ウエートの指数にすると、実は株価が上昇し過ぎた銘柄を多く買う傾向があることが問題になったことがあります。
株価が行き過ぎるとその後下がる傾向が実証で見つかり、時価総額ウエートが不適切という指摘すら出て、時価総額ではなくて資産規模でウエートをかけたほうがいい(Fundamental Index)などという大議論になったこともあります。分かりにくい議論だったようで、いまは廃れたようです。

一方で、資産運用立国などと言われて個人資金がインデックスファンドを買う可能性が高まると、個人投資家の投資目的に合致するインデックスの設計が始まってもよさそうに思います。
指数をどのように設計すべきか、という点について、長期投資の個人投資家が適切に目的意識を持ちやすいように設計することは一つの提案です。そもそもダウ式のような「株価平均」よりも時価総額やパフォーマンスに重点を置いた指数が良い、算出頻度を少なくし、毎日・毎秒算出よりも、毎月程度の算出で心を落ち着かせられる方が良い、などが考えられます。
トレーディング対象としてのニーズを考える場合は、長期投資の個人投資家向けとは言えませんが、先物取引やETFのブランドとなるべく、毎秒算出可能な株価平均が設計されることもあるでしょう。この場合、指数はいかに市場で「ゆがめにくいか」が重要です。質の高い銘柄があるかよりも、指数の一部を構成する低流動性銘柄の大量売買で指数のブレが簡単に生み出せるような指数は設計ミスです。目的に合致させる設計が重要な例です。
これからは、個人投資家の資金の受け皿を充実させようという趣旨での指数設計が始まるとみています。これまでは市場全体を一望したい、年金が正しく運用されているか確認したい、先物取引で使えるブランドが欲しい、などの観点があったのですが、いよいよ個人投資家も自分の目的に合う指数が設計され、それにETFや投信で投資できる時代が来るでしょう。たとえば月に1回しか価格が出ないというのは、ETFとしては不足ですが、機関投資家ニーズなどとの妥協をしながら(参加者が多いほど維持可能性が高いので)、本来の投資を実現できる商品が現れることを期待したいと思います。
資産形成は、インデックス投資中心がいいのか ~神山解説
資産形成にはインデックス投資中心で良いと思います。さまざまなインデックスがすでにある上に、新しく開発されるものも多いので、今後投資家は「選ぶ」必要が増すことになります。どんな場面でもそうですが、常に投資の目的に立ち返ってみてください。引退後の生活を充実させたい、世界の人々の努力と工夫の成果に参加したい、米国のイノベーション力を自らの資産に取り込みたい、といった資金ニーズと性格を組み合わせて、自分に適した指数を選んでください。
インデックス投資の反対として、個別銘柄の選択とテーマ型への投資があります。個別銘柄投資はブレが大きいので、資金の一部をそのような投資にすることが自分の投資目的に合う場合それで良いです。しかし、インデックスでは、「ある銘柄が上がるときに別の銘柄が下がることもある」ため、パフォーマンスは「成功する個別銘柄投資」より低くなることがあります。しかし、ブレはお互いに打ち消しあうので小さくなります。個別銘柄では打ち消しあいがないため、リスクが高いことを知っておきましょう。

テーマ型では、個別銘柄のリスクをまとまった銘柄数で抑えながらも、大きくは特定のテーマに投資します。例えば世界の半導体のバリューチェーンのリスクとリターンに参画する、ロボットに関わる産業に参画するなどです。正直なところ「なぜ半導体?ロボット?」という部分は投資家の知識とインスピレーションに依存します。投資家が職業などを通じて知っている何かに投資する場合、このようなテーマへの投資は適切となるでしょう。今後、よく知られて長く続くと予想される世界経済の成長テーマへの投資機会が増えるのではないでしょうか。
結論としては、ポートフォリオの主な部分に目的に適切なインデックスを選んで投資し、何らかのインスピレーションがあれば、小さい部分で個別銘柄やテーマへの投資を行うと良いと思います。
この記事に関連する日興アセットのETF
TOPIXに連動する成果を目指すETF
1308 - 上場インデックスファンドTOPIX*日経平均株価に連動する成果を目指すETF
1330 - 上場インデックスファンド225*日本の半導体企業関連の指数に連動する成果を目指すテーマ型ETF
213A - 上場インデックスファンド日経半導体株*世界株指数(除く日本)に連動する成果を目指すETF
1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本*新興国株指数に連動する成果を目指すETF
1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)*※上記の*のついている銘柄は新しいNISA制度の「成長投資枠」の対象ETFです。

<解説者>
神山直樹(かみやま なおき)
日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト
2015年1月に日興アセットマネジメントに入社、現職に就任。1985年、日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)にてそのキャリアをスタート。日興ヨーロッパ、日興国際投資顧問株式会社を経て、1999年に日興アセットマネジメントの運用技術開発部長および投資戦略部長に就任。その後、大手証券会社および投資銀行において、チーフ・ストラテジストなどとして主に日本株式の調査分析業務に従事。
【最新のマーケット解説はこちら】
KAMIYAMA Seconds!90秒でマーケットニュースをズバリ解説
●掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また記載内容の正確性を保証するものでもありません。
●当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
●当資料は、投資者の皆様に「上場インデックスファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
●投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
●投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。
●リスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。