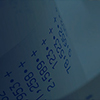マーケット・ビュー
世界のマクロ環境2023年の見通し 10の予測
2023年は類をみない年になる。これまでに類をみない時代に突入しつつあるなか、投資家は、以前の景気・金融市場回復局面に基づく従来型のモデル、特に1990年代中盤以降最も効果を発揮してきたモデルにあまり頼るべきではない。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年11月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は大幅に反発し、米ドル・ベースの月間リターンが18.8%となった。月末に、米FRB(連邦準備制度理事会)のジェローム・パウエル議長が金融政策の引き締めペースを鈍化させる可能性を示したことを受けて、市場センチメントが改善した。
グローバル債券市場2023年の見通し コア市場、新興国債券市場、グローバル・クレジット市場の見通し
明けない夜はない。米国の物価上昇は2022年の夏場にピークを打った模様で、インフレというトンネルの終わりにようやく明かりが見えつつあり、グローバル債券にとって最近の記憶で最も困難な時期の1つが終わりを迎えようとしている。
アジア・クレジット市場 2023年の見通し マクロ環境が引き続き追い風に
023年は良好なマクロ環境が引き続き信用ファンダメンタルズの追い風になるとみている。新型コロナウイルス関連支援を実施する必要性が低下していくなか、アジア諸国の財政赤字は徐々に縮小すると予想される。
グローバル株式チーム 2023年の見通し 今後の新しい時代を切り抜ける
英国では11月から12月にかけて、ほとんどの家庭がクリスマス・プレゼントへの子供たちからの(ときに非現実的な)期待と、家計の経済的な現実に折り合いをつけることに終始する。株式市場も同様に期待と現実が入り混じっており、特に2022年はそれが顕著となっている。
グローバル・マルチアセット2023年の見通し 多極化する世界という未知の領域へ
2022年のことは忘れた方がいいのかもしれない。しかし、資本市場に携わる者にとっては、貴重な教訓を学んだこの年を決して忘れることはできないし、忘れるべきでもないだろう。インフレが猛烈な勢いで復活し、特に10年超続いた過剰な緩和政策(その最たるものがコロナ禍を受けた大規模な金融緩和および財政出動)の急速な解除と相まって、あらゆる資産クラスに大きな痛手をもたらしている。
中国株式市場2023年の見通し ゼロコロナ政策と不動産セクターへの支援が焦点
2022年の中国の状況は不気味なほど2021年に酷似しており、同国株式は2年連続で主要国中パフォーマンスが最も低い市場の1つになろうとしている。世界では多くの国が経済活動の全面的な再開に踏み切ったが、中国はゼロコロナ政策に固執し、ロックダウン(都市封鎖)と大規模な新型コロナウイルス検査の実施は3年目に突入した。
シンガポール株式市場2023年の見通し 不透明な時代における成長の舵取り
世界の投資資産にとって過去数十年で最悪のパフォーマンスとなった2022年は、重大な転換点として記憶されるかもしれない。リターンがプラスとなった資産クラスは稀だったが、シンガポール株式は一面マイナス・リターンだらけのなかでなんとか数少ないプラス・リターン市場の1つとなることができた。
アジア債券・為替2023年の見通し:成長や金融政策引き締めのペースは鈍化へ
2022年は、インフレの高騰に拍車をかける打撃が起こり、世界の各中央銀行がタカ派姿勢にシフトした結果、金融環境が大幅に引き締められるとともに米ドルが非常に大きく上昇した。米FRB(連邦準備制度理事会)は、2022年2月以降にFF(フェデラル・ファンド)金利の誘導目標を合計3.75%引き上げ、総合インフレ率はすでに減速の兆候をみせつつある。
Balancing Act 2022年11月
米国債利回りがピークを打ったと宣言したい投資家たちは、パウエル米FRB(連邦準備理事会)議長が利上げの一時停止やペースダウンを示唆するのに消極的であることに不満を募らせている。しかし、金融環境をタイトに維持して需要を鈍化させインフレを減速させたいというFRBの意向を考えれば、同議長がハト派転換を示唆するとは考えにくい。