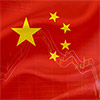株式
Harnessing Change 2025年5月
市場はボラティリティが高い状態ながらも回復基調となり、足元で貿易を巡る緊張の緩和が見受けられるようになっている。しかし、この不確実な状況のなかで唯一確かなのは、何が起こるかわからないということだ。
Harnessing Change 2025年4月
世界貿易の先行きが依然不透明であることから、今後数ヵ月にわたり中国当局による消費や企業活動へのより積極的な政策支援が期待される。ボラティリティが高止まりしているとともに米中間の貿易政策を巡る先行き不透明感はあるものの、状況改善の可能性を示唆する明るい兆しもある。
Harnessing Change 2025年3月
米国政府との貿易戦争が激化するなか、中国は個人消費計画の概要を示すなど国内消費の押し上げを 2025年の最優先課題として重視しており、好ましい方向に進んでいる。米国の政策の不確実性がもたらす世界的な景気減速の悪影響を抑制するには、各国が国内で景気刺激策を実施していくことができるかどうかが重要になる。
進展をみせるベトナム
我々はこの1週間、ホーチミン市で企業やアナリスト、政府関係者と対話したが、投資家のあいだでは慎重ながらも楽観的なムードが漂っていた。ベトナムは、輸出の低迷や債券市場の危機、重大な政変から持ち直して1年が経過し、転機を迎えている。目先の見通しは際立ったものには見えないかもしれないが、現在進められているより深い構造的シフトが、ベトナムを持続的かつ長期的な成長へと導く可能性がある。
Harnessing Change 2025年2月
DeepSeekが中国市場に活気をもたらしており、中国のITセクターは、規制当局による大々的な取り締まりが始まって5年ほど経つなか、2025年に入ってから復活劇をみせている。さらに、追い風となる政策環境が続き、消費主導型経済への構造改革を促進する政策が今後もさらに実施されていくとみられるなか、中国の景気回復と成長が進む可能性は十分にある。
Harnessing Change 2025年1月
1月はDeepSeekが世界で話題となった。この低コストAI(人工知能)モデルの登場を受けて、設備投資を見直す動きが広がる可能性がある。さらにDeepSeekの登場によって、よりコスト効率や拡張性の高い、アクセスしやすいAI環境へのシフトもみられ始めている。また、AIプロジェクトのネックとなっていた多額の設備投資を行うことなく、最先端のテクノロジーを取り入れることができる中国企業が増えていく機会がもたらされている。
Harnessing Change 2024年12月
トランプ次期大統領が新興国市場に与える影響について懸念はあるものの、過去のデータによると中国、韓国、台湾は最も貿易感応度の高い市場であるにもかかわらず、トランプ大統領の第1期の期間にS&P500種指数をアウトパフォームした。ここで得た教訓は、先入観を持たないこと、そしてトランプ氏の大言壮語よりも、大幅なファンダメンタルズの変化が起こり得るということだ。
Harnessing Change 2024年11月
ドナルド・トランプ氏が米国大統領として復帰し2期目を迎えることになり、中国は圧力を感じている。しかし、トランプ前大統領の1期目に、中国株式は米国株式(S&P500指数)をアウトパフォームしており、外部圧力よりも国内政策が重要であることが示されている。
Harnessing Change 2024年10月
トランプ大統領の1期目の任期中において、中国株式市場は米国株式市場(S&P500)だけでなく、チャイナ・プラス・ワンの恩恵を受けたとみられるいずれの国・地域の株式市場もアウトパフォームした。歴史が繰り返されることはないかもしれないが、トランプ氏の2期目の大統領任期中に、中国の国内政策や市場環境が大きな要素となることは明らかである。
道なき道を進み続ける
グローバル株式チームが日興アセットマネジメントに加わり、日興AMグローバル株式戦略を立ち上げてから10年が経つが、その間に世界は大きく変わった。2014年当時、気候変動に関するパリ協定は署名されておらず、グローバリゼーションは台頭し、ドナルド・トランプ氏と言えばテレビ番組で人気が出た有名人として主に知られていた。
Harnessing Change 2024年9月
市場では、米FRB(連邦準備制度理事会)による追加利下げが予想されており、これがアジアの各中央銀行に利下げ余地をもたらし、国内の経済成長にとって大きな下支えとなる。また、中国のさらなる景気刺激策が見込まれるなか、国内外から中国株式への資産配分ペースが加速して、市場全体が押し上げられると予想する。
中国の景気刺激策は十分か?
中国本土の経済は低迷している。若年層の失業率上昇を受けて国内消費が冷え込んでいる一方、家計資産は大部分が不動産に投資されており、不動産価格の下落に伴って大きく目減りしている。コロナ後は、マクロ経済の回復の遅れや欧米との間で続く貿易摩擦が原因となって企業収益が落ち込み、国内株式市場は劣勢に立たされている。
Harnessing Change 2024年8月
当社では、アジア市場の中期的なファンダメンタルズの最大の変化は金利環境のシフトだとみている。労働市場の指標低迷やインフレ指標の沈静化が続くなか、FRBは間もなく利下げを開始すると予想されており、これがアジアに大きな影響をもたらすとみている。
もしもトランプ氏が勝利したら:アジア株式の観点からみた不確実性と機会
2024年11月の米国大統領選挙が近づくなか、ドナルド・トランプ氏が2期目を確保した場合に生じ得る不確実性と機会に焦点を当てながら、アジア株式の観点からみた世界の貿易、経済、地政学的な影響を探る。
Harnessing Change 2024年7月
インドは、アジアにおいて引き続き長期的な成長ストーリーがあり、新たな投資資金を引き付け続けている。一方、中国は投資家心理が好転するポジティブな材料を待っている状態であり、バリュエーションは割安な水準にある。
美容製品から自転車に至るまで前途有望なアジア小型株
世界の美容業界をより規模の小さい韓国企業が席巻するようになったのは周知の通りだ。1990年代に始まった「韓流」の波は、韓国の文化やエンタテイメントの世界的人気に火をつけた。今日、これには美容トレンドも含まれ、「Kビューティ」と呼ばれるスキンケア製品や化粧品で世界の美容トレンドを切り開いている。例えば「グラス・スキン」という言葉は美容意識の高い人々の間で世界的に定着しており、潤いと輝きに満ちた肌にするための10ステップのスキンケア法も広まっている。
Harnessing Change 2024年6月
中国については、ファンダメンタルズのポジティブな変化が実際に確認されてから選好度を引き上げる方針であり、非常に選別的なアプローチを維持している。アジア株式市場は、AI(人工知能)をめぐる熱狂状態やポジティブな構造改革などが相俟って、台湾、韓国、インドを中心に上昇した。
Harnessing Change 2024年5月
欧米は景気サイクル後期にあり、バリュエーションが割高であるのに対して、アジアはサイクルの初期にあり、バリュエーションが割安となっている。このことは、世界の投資家に優れた分散の選択肢をもたらすだろう。
インド総選挙の結果と同国株式市場への影響
2024年のインド総選挙では、出口調査予測や市場予想に反して、ナレンドラ・モディ首相率いるインド人民党(BJP)が239議席しか確保できず、単独過半数に必要な272議席に届かなかった。前回の2019年選挙ではBJPが303議席を獲得していたことから、大幅に議席を減らしたことになる。
Harnessing Change 2024年4月
市場環境はここ1ヵ月で大きく変化した。話題は米国の利下げから利上げの可能性へと変わり、中国株式市場は魅力的なバリュエーションと実効性のある政策実施期待が相まって大幅に上昇している。
Harnessing Change 2024年3月
アジア全体の重大な焦点となっているのは、引き続き中国の経済および株式市場だ。中国の不動産セクターは、依然として脆弱である。しかし中国株式は、財政および資本市場の両方における追加支援策や市場期待の修正を受けて、2023年末から今年1月にかけて見られたパニック売りから回復している。
Harnessing Change 2024年2月
中国株式は、バリュエーションが過度に売られすぎの領域にあることから、ある程度短期的な反発があるかもしれない。しかし、当社では中国の主な住宅分野の問題を解決し得る供給サイドの措置など、相場の上昇をより持続可能なものにする幾つかのドライバーについてモニタリングしている。
エネルギー安全保障とフューチャー・クオリティ
2023年は市場にとって素晴らしい年であった。とはいえ同年、世界は過去最高気温を記録するとともに、数々の大きな気候災害を目の当たりにした。ハワイの山火事、北アフリカの干ばつ、南米で相次いだ洪水、日照り、地震、土砂崩れなど、数え上げればきりがない。筆者が言いたいのは、中央銀行は短期的には金融リスクや市場をコントロールできるかもしれないが、母なる自然にはかなわないということだ。
Harnessing Change 2024年1月
インド市場は引き続き魅力的である。企業収益の成長はアジア地域で最も高水準にあり、バリュエーションは過去のレンジの中央近辺で推移しているほか、経済成長は好調でインフレは抑制されている。
AI競争を乗り切るためのフューチャークオリティ・アプローチ
運用マネージャーとして、最も重要なことの1つであり、最も難しいことの1つは、誤りを犯したことを認めるタイミングを心得ていることだ。投資において、判断ミスはしばしば起こり得る。綿密なリサーチや投資哲学の厳格な適用、規律あるポートフォリオの実行は、リスクを最小限に抑え、長期的に優れたリターンを生み出すことのできる強固な運用ポートフォリオを構築するのにいずれも重要な役割を果たす手段だが、これらは将来を予測することはできない。
Harnessing Change 2023年12月
金利がピークを打ち、また米ドルが高値をつけた可能性があることは、市場全般の好材料になる可能性があり、特に流動性の影響を受けやすい市場や利下げ余地が大きい国、ファンダメンタルズのポジティブな変化が見過ごされてきた分野でこのことが言える。重要な転換期を迎えている中国経済は、高度な製造業やテクノロジー、自給自足、海外のよりハイエンドな市場での成長を促進する経済へと軸足を移しており、当社ではこれらの分野を有望視している。
Harnessing Change 2023年11月
中国は、短期的にはネガティブな材料があるものの、先進製造業やテクノロジーへと軸足を転換しており、引き続き長期投資機会が豊富だとみている。他では、世界で最も有望な成長ストーリーの一部はインドやインドネシアで見出すことができ、また台湾や韓国は半導体産業の回復に伴う緩やかな需要拡大サイクルの恩恵を今後も享受するとみられる。
中国株式市場2024年の見通し
中国株式市場にとって2023年は非常にボラティリティが高い年となり、年間リターンはマイナスとなった。2023年の序盤には、新型コロナウイルス大流行の収束を受けて中国経済の活動再開が急速に進むとの楽観論や大きな期待が広がるなか、中国株式市場のリターンが回復してより安定的かつ堅調に推移していくとの見方が優勢となった。
Harnessing Change 2023年10月
当月もリスクオフの環境が続いたが、当社では現在もアジアで多くのポジティブな材料を見出している。インドのマクロ環境は引き続き良好であり、中国の株式市場は過去20年で最も割安な水準付近にあるほか、半導体産業は底入れの兆しをみせている。米国の金利がピークを付けた可能性があり、これが今後のアジア株式市場にとって歓迎すべき環境になるかもしれない。
超過収益創出の過去と現在
ジョージ・ソロスやジョン・ポールソンのような伝説的投資家には多くのエピソードがあるが、彼等をそれぞれ有名にしたのはたった 1つのトレードだったと言える。
中国とインドの対照的な物価動向
インフレとは、一定期間にわたり経済全体においてモノやサービスの価格水準が上昇することであり、近年は消費者物価が記録的な高水準に達するなかで最も注視される経済指標の1つとなっている。
Harnessing Change 2023年9月
原油価格が1バレル=100ドルに迫り米国債利回りが16年ぶりの高水準に達するなかにあっては、投資家が発作的に守りの姿勢に入るのも無理はない。バリュエーションのばらつきは再び過去最高の水準に拡大しており、長期的な視点に立てば、アジア株式のリスク・リターン・バランスは魅力度を増していると考える。
インドの変革トレンド
今年はこれまでのところ、インドにとって重要な年となっている。3月、インドは第95回アカデミー賞において歌曲賞(アクション映画「RRR」)と短編ドキュメンタリー賞(「エレファント・ウィスパラー:聖なる象との絆」)の2部門で受賞するという快挙を成し遂げた。
Harnessing Change 2023年8月
域内の市場で中国の景気低迷に注目が集まるのは無理もないが、市場に広がっている懸念の影に隠れているものの、アジア地域には長期的に持続可能なリターンをもたらすポジティブな変化の機会が存在すると当社では考えている。中国が乗り越えなければならない問題は克服できないものではなく、システマティック・リスクや社会不安リスクにつながることはないだろう。
Harnessing Change 2023年7月
中国経済にデフレの兆候があるなか、このタイミングで同国政府が成長重視の指示を最近示したことは非常に歓迎すべき兆しだったと言える。こうした政策が実施されれば、構造的な変化につながり、消費者の景況感や中国経済の成長につながる可能性がある。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2023年6月
アジアの大部分においてインフレ問題が落ち着くなか、利下げに動いた中国を除き域内の大方の中央銀行は足下で政策金利を据え置く一方、米国では経済指標が総じて多少軟化するなかでも依然として追加利上げが示唆されているが、当社ではそれ以上に中国の次の動きを懸念している。
現地で見たコロナ後の中国
最近、家族とともに行った2週間の中国旅行は、ある種の「帰郷」であった。飛行機、列車、自動車で(東洋の真珠と呼ばれる)上海、青島、合肥、銀川を巡り、外灘(バンド)として知られる絵のように美しいウォーターフロントの遊歩道で有名な上海へと戻った。
AIは根本的変化を遂げるか
機械学習の成長加速が始まるのに伴い、AIで先発優位性を有する大手テクノロジー企業やAIに特化したハードウェアおよびマイクロプロセッサのハイエンド・メーカー、なかでもアジアの企業が有利な立場にあると考える。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2023年5月
先進諸国が引き続きインフレと経済成長の低迷に苦しむなか、アジアはインフレが十分に抑制されており、金融政策サイクルが欧米諸国に先駆けてピークを迎えているなど、その見通しの明るさが際立っている。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2023年4月
労働力と経済成長が不足している世界において、これら両方を供給できるアジアはより長期的に非常に有利な立場にあるとみている。現在の米国主導の利上げサイクルが終わり、欧米のより脆弱な金融機関の経営不安が払拭されれば、アジアの見通しは明るいだろう。アジア市場は、現在バリュエーションが魅力的な水準にある。
アジアの金融機関:劇的事件の後
アジアの銀行は、各国の利上げの規模が小さいこと、金融規制当局による慎重な舵取り、銀行の高い自己資本比率および総資産に占める有価証券投資比率の健全性を勘案すると、現在の世界的な銀行混乱に巻き込まれる可能性は低いと考えられる。このことは、長期的にはアジアの銀行界にとって好材料であり、魅力を高めるものと考えている。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2023年3月
世界各国が労働力不足の影響もあって成長力が不足する中で、その両方を備えるアジア諸国は、長期的成長のための強固な足場を具備していると考える。現在のアジア株式市場は非常に魅力的なバリュエーション水準にあり、米国が主導している金利引き締めサイクル、及び弱体化している欧米諸国の金融機関の処理が終了した後の先行きは明るくなると考える。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2023年2月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は大幅に下落して米ドル・ベースの月間リターンが-6.8%となり、前月の上昇分がほぼ打ち消された。米国で市場予想を上回る経済指標が発表されるなか、中国の経済活動再開や金利がピークに達したとの前月の高揚感は短期的なものにとどまり、金利は一段と上昇して高金利がより長期化するとの不安が広がった。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2023年1月
2023年のアジア株式市場(日本を除く)は好調な出だしとなり、当月の米ドル・ベースの月間リターンは8.2%に達した。中国株式に対する投資家センチメントの回復が支援材料となった。米国では、CPI(消費者物価指数)上昇率が6ヵ月連続で鈍化し、インフレ圧力が弱まり始めているとの期待が広がった。
中国の下級都市が秘める消費ポテンシャル
世界第2位の経済大国である中国にとって、2022年は過酷な年だった。第4四半期になるまで厳格な新型コロナウイルス対策を維持し、それによって企業の活動が妨げられ経済成長が抑制された。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年12月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は小幅に下落し、米ドル・ベースの月間リターンが-0.2%となった。米FRB(連邦準備制度理事会)は大方の予想通り0.50%の利上げを実施し、中国は新型コロナウイルス関連の制限を緩和する措置を発表した。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年11月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は大幅に反発し、米ドル・ベースの月間リターンが18.8%となった。月末に、米FRB(連邦準備制度理事会)のジェローム・パウエル議長が金融政策の引き締めペースを鈍化させる可能性を示したことを受けて、市場センチメントが改善した。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年10月
決算発表シーズンが市場予想を上回る内容となり、また米FRB(連邦準備制度理事会)が利上げペースを減速させるのではとの慎重ながらも楽観的な見方が広がったにもかかわらず、当月のアジア株式市場(日本を除く)は全体として下落し、月間リターンが米ドル・ベースで-6.1%となった。
明るい見通しのアジア株式市場
2022年、アジアの多くの国を含む世界各国は数多くの障害に直面した。インドやインドネシアなどの例外を除きアジア市場のパフォーマンスは概して良くない。2021年末時点では、2022年はもっと明るくなるという展望を描いていた投資家もいた。しかし、今のところ、そのような見方は楽観的過ぎたようで、MSCIオールカントリーワールドインデックスは変動の激しい状況が続き、年初来20%下落している。年内の世界市場は、各国中央銀行の金融政策とロシア・ウクライナ戦争など地政学的動向に左右されるだろう。
中国全国代表大会を踏まえた市場見通し
中国共産党第20回全国代表大会(全国代表大会)が2022年10月23日に閉幕し、習近平国家主席の三期目続投が予想通り確定した。毛沢東以来の権力を手に入れたことに加えて、中央政治局常務委員のうち習近平氏を除く6名全員を自身への忠誠心が強いメンバーで固めることにも成功した。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年9月
当月のアジア(日本を除く)および世界の株式市場は、金利の上昇やインフレの高まりが引き続き重石となった。米国では、8月のCPI(消費者物価指数)上昇率が前年同月比8.3%と市場予想を上回ったことに加え労働市場が逼迫していることを受けて、FRB(連邦準備制度理事会)が0.75%の利上げを実施した。
見事な復活:盛り返すアジアの小型株
約10年にわたり、大企業の陰に隠れて目立たなかった小型企業が見直されている。小型企業の重石となっていた要因が、今や追い風に転じつつあるなか、当社では当該資産クラスの盛り返しに弾みをつけるとみられる7つの重要な進展を特定した。
アジア株式の視点から見たESG投資
ESG 投資ほど、短期間で幅広い投資家の心を捉えた投資アイデアはない。特に近年では、ESG投資の普及が急激に加速している。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年8月
米国では、7月のCPI(消費者物価指数)上昇率が前年同月比8.5%となるなどインフレが高止まりしていることを受けて、FRB(連邦準備制度理事会)が利上げによるインフレ抑制を優先する方針を維持した。追加利上げ圧力をさらに強めたのは労働市場の逼迫で、7月の求人数が増加を示し失業者1人当たりの求人件数が2件となった。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年7月
米国の足下のCPI(消費者物価指数)上昇率が前年同月比で9.1%と40年ぶりの高水準となるなか、米FRB(連邦準備制度理事会)は0.75%の利上げを実施した。また、米国の2022年第2四半期のGDP成長率が年率換算で前期比-0.9%となり、米国経済がテクニカル・リセッション(2四半期連続のマイナス成長)入りしたことが示されると、市場の懸念が強まった。こうしたなか、当月のアジア株式市場(日本を除く)は下落し、月間リターン(米ドル・ベース)が-1.2%となった。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年6月
当月は、リセッション(景気後退)や前年同月比8.6%と40年ぶりの高い伸びとなった米国の5月のCPI(消費者物価指数)への懸念が、様々な国に波及的影響をもたらした。アジア株式市場(日本を除く)は、米国の複数の逆風材料を警戒するとともにインフレを域内共通のテーマとして下落し、月間リターン(米ドル・ベース)が-4.5%となった。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年5月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、米FRB(連邦準備制度理事会)が指標となる翌日物金利を0.50%引き上げたものの、上海市が新型コロナウイルス関連の規制を解除するとの方針を発表したことが好感されて小幅に上昇し、米ドル・ベースの月間リターンが0.5%となった。
成長を収穫し変化を活かす 2022年5月
変化は、アジア市場においてより一般的かつ際立っている。その理解に努めることは、持続的リターンをもたらすために不可欠である。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年4月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、インフレや米FRB(連邦準備制度理事会)の利上げ幅が従来の予想を上回る可能性をめぐり投資家のあいだで懸念が広がるなか、下落して米ドル・ベースの月間リターンが-5.2%となった。
中国からの現地目線での考察
海外移住者のなかには自らの出身国とのつながりをめぐるジレンマに直面する者もいるかもしれないが、シンガポール在住中国人の筆者は、母国とのつながりがなくなったと感じたことが一度もない。その一因は、進化しているインターネット技術によってタイムリーなニュースが配信されてくることや、中国最大のSNSである微博(ウェイボー)を使い続けていることにあるが、したがって、「中国の特色ある社会主義」は依然として筆者に影響を及ぼしており、筆者の存在意義の支えとなり続けている。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年3月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、ロシア・ウクライナ紛争が嫌気されたのに加え根強いインフレ懸念も重石となって下落し、月間リターンが米ドル・ベースで-2.8%となった。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年2月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は下落した。ロシア・ウクライナ間の緊張激化の結果、ついにロシアがウクライナ侵攻に踏み切ったことが嫌気されたのに加え、根強いインフレ懸念も株式市場の重石となり、月間リターンが米ドル・ベースで-2.3%となった。
変化を活かして 成長を遂げるインド
帰省できなかった2年間を経てインドに帰り1ヵ月を過ごした私は、そこでの新常態に良い意味で驚かされた。コロナ禍は大きな苦難となってきたが、テクノロジーの普及などを中心にポジティブな変化も引き起こしている。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2022年1月
年初のアジア株式市場(日本を除く)は、根強いインフレを受けて米FRB(連邦準備制度理事会)の引き締めサイクルが予想されたよりも積極化するかもしれないとの懸念から、厳しい展開を迎え月間リターンが米ドル・ベースで-3.10%となった。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2021年12月
12月のアジア株式市場(日本を除く)は、米FRB(連邦準備制度理事会)が3月に債券の購入を終了すると述べるとともに、根強いインフレに対処すべく2022年中に3回の利上げ実施を示唆したにもかかわらず、米国株式市場に連れ高となり、月間リターンが米ドル・ベースで1.4%となった。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2021年11月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、新型コロナウイルスの新たなオミクロン変異株の流行拡大によって、世界各国の国境再開計画が見直しを迫られ、景気回復が遅れるかもしれないとの懸念を受けて下落し、月間リターンが米ドル・ベースで-3.9%となった。
Harvesting Growth, Harnessing Change 2021年10月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は上昇し、月間リターンが米ドル・ベースで1.4%となった。投資家の注目は引き続き、インフレ圧力の高まりや米FRB(連邦準備制度理事会)によるテーパリング(量的緩和の漸進的縮小)計画に集まった。
アジア株式 Monthly Outlook 2021年9月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は下落し、月間リターンが米ドル・ベースで-4.2%となった。中国の経済成長見通しに対する懸念や米FRB(連邦準備制度理事会)のテーパリング(量的緩和の漸進的縮小)計画が、市場センチメントの主な悪化要因となった。
アジア株式 Monthly Outlook 2021年8月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は上昇した。月初は新型コロナウイルスのデルタ変異株の感染拡大に対する懸念が市場の重石となったものの、月末にかけては米FRB(連邦準備制度理事会)のハト派的な発言や打撃を受けていた中国のテクノロジー・セクターの反発が市場センチメントを押し上げ、月間リターンは米ドル・ベースで2.3%となった。
アジア株式 Monthly Outlook 2021年7月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、中国での個別学習指導事業およびテクノロジー関連セクターへの政府による規制強化を受けて同国株式が売り込まれたことが重石となり、下落して米ドル・ベースの月間リターンが-7.5%となった。域内諸国で新型コロナウイルスの感染者数が再び増加したことも、アジア株式に対するセンチメントを悪化させた。
アジア株式 Monthly Outlook 2021年6月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、域内で新型コロナウイルスの感染者数が最近急増していることなどが重石となり、小幅に下落して月間リターンが米ドル・ベースで-0.1%となった。インフレの加速をめぐる根強い懸念や、米FRB(連邦準備制度理事会)のテーパリング(量的緩和の漸進的縮小)が予想よりも早く実施されるのではとの不安も、市場センチメントを冷え込ませた。
アジアの小型株で好リターンを獲得
日興アセットのアジア株式チームのメンバーでシニア・ポートフォリオ・マネジャーであるグレース・ヤン氏が、Citywireのアジア部門ベスト・ファンド・マネジャー賞受賞という最近の栄誉の背景にある潜在的理由や、アジアの小型株分野で隠れた珠玉銘柄を発掘することに対する同氏の情熱について語ってくれました。
アジア株式 Monthly Outlook 2021年5月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、域内の複数国での新型コロナウイルス感染者急増に対する懸念や根強いインフレ不安をよそに、同地域で継続中の景気回復をめぐる楽観ムードを追い風として底堅い推移を見せ、月間リターンが米ドル・ベースで1.2%となった。
アジア小型株の投資魅力
アジアの小型株は、大型株を長期的にアウトパフォームしてきた実績があるとともに伝統的株式ポートフォリオに優れた分散効果をもたらすことから、長期スタンスの投資家にとって多くの投資メリットがあると考える。
アジア株式 Monthly Outlook 2021年4月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、中国その他複数の域内諸国で2021年第1四半期のGDP成長率が市場予想を上回ったことなどを受けて同地域の景気回復をめぐり楽観ムードが広がるなか、まずまずの上昇を見せ月間リターンが米ドル・ベースで2.5%となった。
新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)で大騒ぎとなった2020年を経て、2021年の世界の経済成長はワクチン接種のポジティブな進展と政府による継続的な対策を背景に回復すると予想される。しかし、回復ペースは国によって差が生じるとみられるとともに、新型コロナウイルスの再流行の不安は根強く残っており、ついに危機を脱したなどと言うのは僭越だろう。
アジア株式 Monthly Outlook 2021年3月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、根強いリフレ懸念や世界的な債券利回りの上昇といった逆風材料がCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)のワクチン接種進展に伴う地域経済の回復期待を上回ったことから、利益確定売りに押されて月間リターンが米ドル・ベースで-2.5%となった。
アジア株式 Monthly Outlook 2021年2月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)のワクチンが域内に景気回復をもたらすとの楽観ムードが投資家のあいだで続くなか、上昇して米ドル・ベースの月間リターンが1.2%となった。
アジア株式 Monthly Outlook 2021年1月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、新型コロナウイルスの新たな変異種によってもたらされた不透明感をよそに上昇し、月間リターンが米ドル・ベースで4.1%となった。
アジア株式 Monthly Outlook 2020年12月
当月のアジア株式市場(日本を除く)は、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)のワクチンが世界的な景気回復をもたらすとの楽観ムードや米国の追加財政出動、中国の堅調な経済指標を追い風に着実な上昇を見せ、月間リターンが米ドル・ベースで6.8%となった。